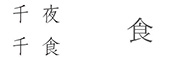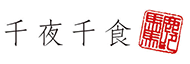京都祇園「八寸」
はじめて訪れた店であるが
厳選された贅沢素材をふんだんに使いながらも
渋地味という洗練具合で唸らせてくれる店である。
年末の連休あたりでいつも南座へ行く。もちろん顔見世を観るためである。と同時に今年最後の京都の懐石を食べるというイベントも兼ねている。今年は、いつものあの店がうっかり油断しているうちに満席になってしまい、難民になってしまった。この際、チャレンジしたいリストにある店に片っ端から電話したが、すべてアウトである。ふと、東京の友人がここはいいと言っていたことを思い出し、ダメもとで電話したら運良く空いていた。
新しい店。祇園。お墨も付いている。わくわくしながら、のれんをくぐると、そこにはどっしりした奥行きのあるカウンター。うん、このスタイルは大好きなのだ。カウンター後ろの食器棚の上には、年季の入った趣味のよい大皿が飾ってある。鴨をかたどった陶器もある。雰囲気、うつわのセレクトともに、嫌じゃない。カウンターの真ん中あたりに案内される。全12席。中で立ち働く人は4名ほど。ご主人であろう方は、常連客の相手に余念がない。適度なにぎわいとざわめきがあり、非常によい雰囲気である。料理が楽しみになってきた。
先付けにはこのわたの茶碗蒸し。ううむ、これは渋いな。しょっぱなから、私の好きなところを突いてくる。またこの漆のうつわが、さりげないのに洗練されている。こういう漆器で蒸すのは、温度調節など技術がいるのではないだろうか。八寸は、間人のこっぺがに。いわゆるせこがにであるが、この間人という名前は関西では松葉蟹の最高峰として燦然と輝くブランド中のブランドである。贅沢に外子までついており、そのメインの蟹に牛蒡の鰻巻き、鴨ロース、琵琶湖のもろこ、なまこにこのこ、からすみ大根がコーディネイトされている。
少し脱線するが、間人は「たいざ」と読む。この地名にぴんと来た人は、間違いなく歴史好きであろう。そう、かの聖徳太子のご母堂であらせられた間人(はしひと、はしうど)皇后が、一時期この地に行啓され、去られるときにおん自らの名を贈ったといわれている。しかし、土地の者達、いくらなんでも皇后の御名をそのままお呼びするのは畏れ多いとして、皇后が退座されたのにちなんで間人を「たいざ」と読み替えたというのである。もちろんこれは伝承である。だが、ロマンティックな話ではないか。上古の時代と今とが丹後ではいまだ地続きであるのだ。こういう物語は痺れるし、蟹の季節になって間人蟹という名前を聞くと、いつもこの物語を思い出す。
料理に戻ろう。いや、その前に本日の酒。澤屋まつもとという純米。伏見にこんな旨いのがあるなんて知らなんだ。酒はこのまつもと一本なのだそうだ。お造りは、鯛、アオリイカ、カンパチに赤貝。鯛をまるでてっさのように、盛りつけている。皿の赤と緑が透ける効果を狙った心憎いしつらえである。即全らしき赤絵のうつわ、ほ、ほしい。そしていよいよお椀だが、この漆の椿の見事さといったらどうだろう。蓋をあければ、す、すっぽんのおつゆである。くっきりと澄んだお出汁。すっぽんの滋味は、清涼であるのに濃厚。いのちをいただいているというしみじみした心持ちになる。
青白磁のうつわには、巻き湯葉。しっとりと出汁を含み、噛めばじんわりと旨味が滲み出す。陶器のお椀の蓋をあけると、中には京の冬の定番、ぐじの蕪蒸し。南座の顔見世と蕪蒸しは間違いなく師走の風物詩として私の中ではセットになっている。今年も一年、無病息災で過ごせたことに心の中で感謝を捧げながらいただく。さて、再びおでましになったのは、間人蟹様のおみ足である。蟹味噌と優雅に和えた身も出される。ああ至福。ああ絶佳。淡路の鯖鮨は、まるまる太って脂ののった鯖を軽く〆、松前昆布を巻いた一品。あまりの旨さにこれはもうひとつ別にテイクアウトすることにする。最後は猪のすき焼き仕立て。これを自然薯のたれでいただく。猪の野性味を自然薯に合わせるという発想が素晴らしい。野生には野生を。動物と植物であっても、生命力のあるものどうし、見事なまでのマッチングである。
デザートはラ・フランスと苺のジュレがけ。この唐津は、中里隆さんっぽいな。それにしても、こちらのうつわ、すべてが渋い趣味で、ひとつひとつ素晴らしいものを使っているが、使いこまれていてまったく「どや」という威圧感も嫌味もない。それでいて手に取ると、ひとつひとつ吟味して、料理に合わせているのがよくわかる。こういうのをほんまもんの洗練というのだろう。
この店も、当然お気に入りリストに入れる。また、通いたい店が増えた。