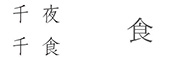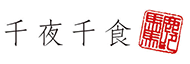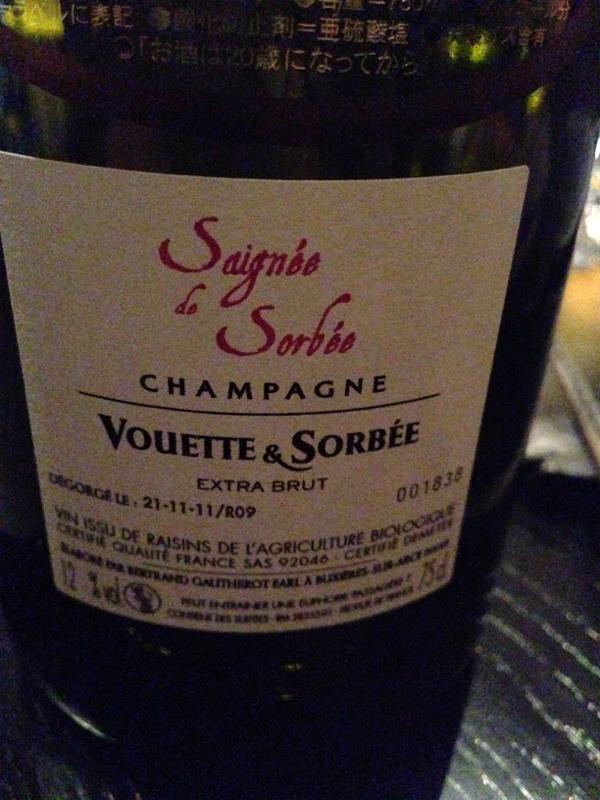Noma@マンダリン
1月の申込にことごとくハズレて
がっくりしていたら、ホテルから案内が。
宿泊と抱き合せではあるが、これは行かなくちゃ。
今年初頭のグルメな噂のなかでダントツのぶっちぎり(失礼)だったのは、何と言っても「Noma」の上陸だろう。コペンハーゲンのお店を一ヶ月休んで、スタッフ全員で東京に来るのだという。
「Noma」の何が凄いかっていうと、「世界のベストレストラン50」でなんと1位を4回もとっていて、世界一のレストランとしてその名を轟かせているからである。しかもシェフのレネ・レゼピはあの「エル・ブリ」の出身なのである。「エル・ブリ」というのは、スペイン、カタルーニャ地方の山の中にあるレストランで、50席しかないシートに年間200万件もの予約が殺到していたと言われる世界一予約が取れないレストランで、その独創的な料理は世界中の料理人に影響を与えたと言われている。今やすっかりポピュラーになっているエスプーマ(食材をムースのような泡状にして出す)を考案したのも、この「エル・ブリ」のシェフである。ところがこの店は2011年の夏閉店したのである。その心意気を引き継いでいるのが「Noma」なのである。
いつかは行ってみたかった「エル・ブリ」。わざわざカタルーニャ地方まで、そのためだけに出かけて行くなんて食いしん坊にとっては究極の贅沢である。でも、もうできなくなってしまったのである。で、「Noma」であるのだが、コペンハーゲンにあるこの店だって、予約はまったく取れない。それが、日本に来るのである。少々お高くたって、行かなければならんだろう。
しかし、1月の抽選には外れた。地団駄踏んでもどうにもならぬ。ところがある日、東京のホテルを予約するのに利用している一休からスペシャルな案内が届いたのである。大好評につき、2月も少しだけ営業を延長するのだという。「Noma」が店を出しているのは、日本橋のマンダリンオリエンタルホテル。その宿泊とセットなら、まだ席が取れる可能性があるのだという。宿泊料とセットになったかなり強気の値段ではある。しかし、コペンハーゲンまでわざわざ行くことを考えたら、ある意味リーズナブルとも言えなくもない。さっそくスケジュールをチェックすると同時に、こういうのにつきあってくれる友人も抑え、申し込んだらあたったのである。
そうこうするうちに、1月すでに行った人のブログなどがあがりはじめ、どうやら蟻を食べさせるらしいということがわかってきた。蟻ですって?好き嫌いのない私であるが、好んで虫を食べる趣味はない。一体全体どういう料理を出すんだろう。めらめらと食い意地が燃えて来た。万全の体調を持ってして臨まなければいけない。
さて、当日。申込の条件として相席とあったので、6人がけの丸テーブルに三組である。相客に軽く会釈をして、ドリンクメニューを見せてもらう。事前にワインとドリンクのペアリングの告知もあったが、なにしろワインが24700円、ドリンクでも16500円である。ふーん、これはあり得んぞ。それよか好きなシャンパンやワインをボトルで飲んだ方がいいわ。なので、シャンパンをお願いする。ヴェット・エ・ソルベ。シャンパンというよりドライなワインのような味わい。これ、イケる。
一皿目。噂の蟻である。氷を敷き詰め、そのまわりには貝殻をずらりとデコレーション。赤いプレートは渋い漆器である。中央に鎮座するのは北海道のぼたん海老。海老のまわりの黒いのが長野の蟻である。蟻には独特の酸味があって、これが海老に絞るレモンとか酢橘のかわりになるのだそうだ。だから、口に入れると蟻のシャリっとした感触はあるものの、軽い酸味は別に嫌じゃない。もちろん手づかみで食す。さすが、バイキングの国から来ただけのことはある。ワイルドだ。
二皿目。柑橘類をサラダ仕立てにしたもの。八朔、文旦、タンカン、みかんを切って、昆布出汁とオイルにピパーチという島コショウを混ぜたドレッシングがかかっている。山椒がピリリと利いた味。これを漆塗りのスプーンとフォークでいただくのである。素材のセレクトに日本への敬意とサービス精神が横溢している。うつわやカトラリーの選択にもメッセージがある。
三皿目。漆盆の上にナプキンが折りたたまれ、その上に乗っているのはあん肝トースト。あん肝を凍らせたものを薄く削っているのである。口に触れると体温でぬめっととけていく。もちろん、これも手づかみである。どんどん気持ちが野蛮人になっていく。
四皿目。「タ・コ・ヤ・キ〜」と言いながらデンマーク人が持ってきたものは、たこ焼きではなく、イカソーメン?いや、イカそばである。順番を間違えたな。なんとこれは甲イカを蕎麦のように切り、上にイカのわたを発酵させているソースを塗っている。この蕎麦を松の香りをつけた出汁に石垣島の薔薇を散らしたものにつけて食べるのである。黒々したイカをピンクの薔薇につけるなんて。なんちゅう発想。日本人ではこうはいくまい。良いとか悪いとかではなく、アイデアがぶっ飛んどるわな。ちなみにこのお箸をプロデュースしたのは、三角屋の三浦さんである。黒檀でできた希少な一品だ。
五皿目。北海道馬糞雲丹のタルト。これもナプキンの上に乗っているので、当然手づかみである。台は羅臼昆布の粉末を練り込んだ生地。雲丹の下にはサルナシのペーストが敷かれている。このサルナシ、キウイの原種で(五回會のとき「本湖月」のデザートではじめていただいた)すっぱ旨い。ふっくら芳醇な雲丹との相性はなかなかよい。
六皿目。作り立ての豆腐の上に、くるみ、味噌、柚子を乗せて。豆腐がまったり溶けていく。生のくるみの食感も、しゃりしゃりして面白い。
七皿目。二日間干した帆立の貝柱をピューレ状にし、バターと蜂蜜を加え、ホイップし冷凍している。こうすることで、まわりにはショワショワの泡状のものがつき、食べるとまるで揚げ煎餅のような不思議な触感が生まれる。仕上げに昆布オイルとごま油を少々。こういうのはもうサイエンスの世界である。どんだけ実験したんだろうな。
八皿目。南京。かぼちゃである。カツオ出汁で似たかぼちゃに、ローストした羅臼昆布の細切りを並べ、桜の花の塩漬けをデコレーションした一品。ソースはとろりとしたバター風味に桜の木のオイルを浮かべて。
九皿目。フワラーガレット。黒にんにくをつぶして葉っぱのカタチにしてる。しかし、これが不味いのなんのって。オーストラリアのベジマイトって知ってます?あれを初めて食べたときと同じくらいのオーマイガッドな衝撃。うえ〜って感じ。箸休めでも、口直しでもない、摩訶不思議なブレイクである。もちろん、全部食べたけどね。
十皿目。根菜の盛り合わせ。むかご、クワイ、百合根、ちょろぎ、蓮根、牛蒡。これを味噌漬けの卵黄につけて食べる。ソースは焼き昆布の出汁にアーモンドを加えたソース。これは楽しいし、日本で昔から親しまれてきた根菜のよさを外国人のシェフに教わっている感じ。忝ない。
十一皿目。メインである。なんと、野生の鴨の丸焼きである。網で獲った鴨を三週間熟成させているそうだ。これをまずは丸ごと見せてくれる。ファンキーでワイルドな演出である。その後、部位ごとにちゃんと切り分けてくれ、マツブサの実のソースで食べる。鴨は大好きなので、ウハウハ言いながら食べたけど、向かいに座っている人にあてがわれた鴨は生焼けでほとんどピンク色であった。連れが、野生の鴨の生はいろいろ寄生虫があるからなあ、などと恐ろしいことを言う。聞こえてるってば・・・それにしても、それを食べるのは苦行だったろうなあ。
十二皿目。イーストと椎茸のなかで炊かれたカブ。ううむ。十三皿目。米でつくったアイスクリーム。麹と柚子風味。白いのはサクサクしたお米の煎餅。鴨の口直しとしては蟻、もといアリである。十四皿目。砂糖で丸一日煮込んだ人参芋。キーウィのソースで食べる。もう似たようなかぼちゃ食べてるし・・・別にさつまいもをご丁寧に味付けしなくても・・・・
十五皿目。発酵させたセップ茸をチョコレートでコーティングしているのだが・・・苔のボウルの上に素晴らしいデコレーションで乗っているのだが・・・小枝はワイルドシナモンなんだが・・・味の想像を超えて、うえ〜。不味い。ま、これはご愛嬌であるな。
全十五皿。
普段我々が使わないような知らないような日本の食材まで綿密にリサーチして取り入れているその執念と探究心には圧倒された。これは美味しいとか旨いという次元を超えたシェフ、レネ・レゼピの高次元なパフォーマンスであり、プレゼンテーションであり、食べることのできる一瞬のアートなのだろう。一皿、一皿にこめられた創作への熱情は、たしかにひしひしと伝わってきた。世界一の評価というのは、その飽くなき好奇心と面白いものを独創的に表現してやろうという精神に捧げられているのではないか。レネによる度肝を抜くアミューズを一度は経験してみたいという人は世界中には確かに大勢いるだろう。もちろん、私もその物好きの一人である。