小鹿田焼の皿。
まだ民藝というものを意識する前に手に入れた皿である。こちらも湯布院で出会った。古伊万里とは対照的な素朴さと力強さがあり、そのどっしりとした存在感に惹かれ、大小の皿と、緑釉のかかった深めの皿をそれぞれ二枚ずつもとめた。
「打ち刷毛目」と「飛び鉋」。小鹿田焼(おんたやき)は刷毛や鉋を使いうつわに独特の文様を刻むのが特徴で、飛び鉋の本歌は宋の修式窯飛白文壺であると言われている。焼かれているのは大分県日田市の山間にある小鹿田地区であることから、この名前がついている。窯が開かれたのは江戸時代。三百年以上の歴史があり平成七年には窯場として初めて国の重要無形文化財に集団指定されているにもかかわらず、陶工たちは作品に銘を入れない。
柳宗悦の「日本民藝美術館設立趣意書」にはこう書かれている。
『 概して「上手」のものは繊弱に流れ、技巧に陥り、病疫に悩む。之に反し名無き工人によって作られた下手のものに醜いものは甚だ少ない。そこには殆ど作為の傷がない。自然であり無心であり自由である 』
反復の作業を続けていくうちに、その繰り返しの仕事が陶工たちの手の熟練を促し、自我が入らない無心の美をもたらしたのだとしたら、このうつわたちはまさにそれを体現している。手に入れてから三十年以上になるが、普段の食事を盛るのにどれだけ使ったか。何を入れてもなじみ、荒っぽい扱いにもにも耐え、一枚として欠けていない。代々その家で使い続けられていくうつわとはこのようなものかもしれないし、これこそが「用の美」というものだろう。
奇しくも、これを書いているときに、日曜美術館新春スペシャル「にっぽん、美の旅」で井浦新が小鹿田の窯元を訪ねる番組を観た。現在ではわずか14軒、そのうちの10軒が昔ながらのやりかたで今も焼ものを作り続けている。この地に伝わる形や模様をたんたんと守っているのだ。小鹿田の土を使い、川にある水車を使い唐臼で土を打ち、その土を女たちが何度も漉し、きめ細かく粘りのある土をつくるのである。陶土にするには、乾燥させ一ヶ月以上かかるという。そうやって女たちがつくる陶土を、今度は男たちが引き取って、形作り、文様を入れ、焼き上げる。気の遠くなるような作業は、紛れもなく家内制手工業である。ひっそりと、たんたんと、無心に、作り続けているのである。ある陶工の言葉が印象的だった。「自然体のみで成り立っているので、自分たちが自然に合わせていくんです。薪も二年以上乾燥させるんで大変ですけど、作業がときに神や仏の領域に近づくことがあって、自然界から教えてもらうことは多い」その陶工の名前は、「工」というのだった。
この飾り気のない「用の美」を、これからも、日々の暮らしのなかで使いこんでいきたい。

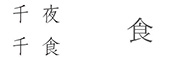




 にほん数寄 『うつわ』その2
にほん数寄 『うつわ』その2 ![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/13-e1406996220656-225x300.jpg)
![写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/32-e1406996306220-225x300.jpg)