京都祇園「千ひろ」
限りなく水のようでいて、ほのかな滋味を感じる出汁。
この煮物椀が、すべての味の基準になっている。
通ってけっこう長いが、いつもその完成度は変わらない。
祇園に名店はいろいろあろうけど、ここがいちばんと決めるのはなかなか難しい。だが、初めて行っていいなと思えば、しばらく通ってみるということは必要だと思う。和食の場合はとくに季節ごとの素材によって都度都度印象は変る。ただ、ファーストインプレッションでいたく感動した店はだいたいいつ行っても、その感動をキープできる確率は高い。前はそうでもなかったのに、突然よくなるということはほとんどない。
ここの煮物椀をはじめていただいたとき、その味に驚いた。限りなく水のようで(厳密には白湯だが)、ほのかに旨味を感じる絶妙の味。これが京都の出汁か、としみじみと思ったことはよく覚えている。京都が好きな母をはじめて連れて行ったとき、「あ〜私長い間生きているけど、こんなおいしいおつゆは生まれてはじめて飲んだ」と言わしめた味である。カウンター割烹のつねとして、ほとんどの下ごしらえは奥の厨房でなされ、最後の盛り付けや造りだけを目の前のカウンターでご主人がさばく。だが、煮物椀の出汁だけは、目の前で何度も吟味しながら実に細かくつくっている。母が「あんなに何度も味見して、あの味になるんやね」と言ったが、まさしく季節やその日の温度や湿度、前後の料理に合わせてその加減を微妙に変えているということだろう。丁寧かつきめ細かな微調整は、いつもぎりぎりまで行われる。
この作業を見るたびに、煮物椀がいかにその店を代表する一品であるかを思い知らされる。そして今のところ、私はここの味がいちばん好きである。いちばん好きということは、他の店に行ったとき、ここの味が基準になるということでもある。
さて、初夏の「千ひろ」である。広島のじゅんさいの上に雲丹が乗っている。じゅんさいの中にはデラウェアが隠れている。デラウェアというのに驚くだろうが、こちらは葡萄とか桃とか果物をうまく使う。美しい藍の皿には白バイ貝。堂々たる歯ごたえがある。中国童子が踊っている絵皿には蛸のやわらか煮。織部に盛られているのは鳥貝の酢味噌和え。先付けがひと皿ずつ出てくる趣向である。三つの小皿は上からはまぐり、白味噌に漬けた鯛、一寸豆。造りは、鯛、たいらぎ、マグロである。マグロの下にはとろろと海苔が重ねてあり、お好みで一緒に食べる。細かく切った塩昆布は、鯛によく合う。
そして、本日のお椀は間人(たいざ)の夏すっぽん。すっぽんが種なのでいつもの出汁ではないのだが、間人ものをいただけるのであれば文句はない。口福にくらくらしつつも、最後の一滴までずずいと飲み干す。焼き物は時不知(ときしらず)。春から夏にかけて穫れる貴重な鮭で、脂が乗っているのにすーうっと舌の上で溶けていく。たっぷりかけられた白いのは生湯葉を擦ったもの。下にはキイウィとレッドグローブという葡萄が隠れている。果物第二弾。笹の葉が描かれた角皿には安曇川の稚鮎。琵琶湖の鮎はやはり京都では最上とされる。なんとよい苔の香りなのだろう。付け合せがバナナというのもこの店ならでは。最後は名物の焼き茄子。白胡麻たっぷりのたれでいただく。お椀がすっぽんだったので、最後はすっぽん雑炊。おなかがパンパンなのに、これも食べずにはいられないし、全部きれいに平らげてしまう。なんとも贅沢な初夏のコースであった。デザートはおなじみのリンゴとオレンジのジュース。
京都では新しいカウンター割烹も増えており、機会があれば行ってみたい名店も何軒かはまだあるのであるが、やはり一軒というなら私はこちらである。まだ、この店を超える煮物椀の味を私は知らない。

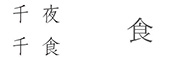




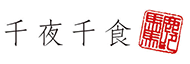
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真101-225x300.jpg)
![th_写真[13]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真131-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真53-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真23-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真62-225x300.jpg)
![th_写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真83-225x300.jpg)
![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真110-225x300.jpg)
![th_写真[15]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真151-225x300.jpg)
![th_写真[11]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真112-225x300.jpg)
![th_写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真91-225x300.jpg)
![th_写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真121-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真33-300x225.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真42-225x300.jpg)
![th_写真[7]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/12/th_写真73-225x300.jpg)
