長門駅前鮨「はしもと」
予約なしでふらりと入る店では
互いの素性を推し量る独特の緊張感があるのである。
「 出合・居合・具合 」のよろしい鮨。
どこに行っても鮨屋があれば、つい行きたくなる。鮨屋には地元で穫れる魚がある。地酒もある。その土地ならではの作法や独特の食べ方もある。鮨を通じてだって、日本の文化人類学は楽しめるのである。地方でも都市ではなく、こういった鄙びた駅前(失礼)の鮨屋とはいったいどういう具合になっているのか知りたくてたまらない。
文楽終了後、長門駅発の電車に余裕があったので、タクシーの運転手さんに駅の近辺に鮨屋があるかどうか聞いてみた。すると「はしもと」を推奨され、横付けしてくれたのである。時間はまだ早いので予約なしでも大丈夫であろう。むろん、店内はガラガラで私一人だけだった。家族経営らしく、おかあさんのような人が相好を崩し、どうぞ、どうぞと招き入れてくれた。カウンターの中程に陣取る。
さてと。店内を見渡すと獺祭があるではないか。さすがに磨き二割三分はないがちゃんと純米大吟醸の50というのがある。たしかに、地元の酒が地元で飲めないのなら地酒の意味はない。「音信」でも、磨き二割三分は宿泊者二本限定で販売していた。さっそくグラスで所望する。
おかあさんが、「私のつくった鯵の南蛮漬け、食べてな〜」とスペシャルな一品を出してくれる。こういう出合はたまらない。はしもとさんちの鯵、もとい味。たまねぎなんぞざくざくと切られてい、酢加減もきわめて素朴なおふくろの味。こういうお惣菜を鮨の前にいただくと舌が違う方向に行ってしまうよと思いながらも、ご好意に甘える。これをアテに獺祭を飲むというのはご当地ならではのファンキーなスタイルではなかろうか。
鮨の前にやはりツマミ系は行きたいので、おすすめの刺身を盛り合わせにしてもらう。はまち、ヒラメ、鯛、カワハギ、ホタテ、金目鯛・・・。とくべつにこの辺だけで穫れる魚はないけれど、この椀飯振舞っぽいひと皿を独り占めできるのはお大尽気分である。そして上握り10カン。シャリは少し少なめにしてもらったが、けっこうなボリュームである。きわめて真っ当な握りの盛り合わせ。それでも軍艦の中にヒラメの縁側が入っていたりすると、おおうなんだかこのスタイルご当地ねえという気分になってくる。
こういったはじめての店にひとりで入り、酒を飲んでいると、たいていはこの女何者かと誰何されることが多い。もちろん近頃のことであるので、そうあからさまに聞いてくる訳ではないのだが、それでもどうしてこんなところで飲んでいるのか、何のためにこの地に来たのか、鮨はどこどこに行っているのかなど、けっこう質問攻めに合うのである。こういうのは、居合いのようなものだと思っている。饒舌にならず、言葉少なに、こちらの正体をうまい具合に想像させる。今回は文楽を鑑賞しに神戸から来たというと急に態度がフレンドリーになった。というのも、こちらの大将は神戸でも修行をしていたとのこと。話をしていると共通の知っている店があったりしてそれはそれで愉快であるし、長門の文楽というのは今や夏の風物詩であるらしい。それだけで距離がぐんと近くなったりする。
カウンター後ろの座敷に入って来たカップルが、あ、こっちも獺祭をとリクエストしながら、しきりに近頃獺祭が気軽に飲めなくなっていることを嘆いている。今や、地元でも手に入りにくくなっているらしい。こういう現象、獺祭だけじゃない。大間のマグロだって地元の人はほとんど食べられないらしいし、松葉ガニや越前ガニ、関サバとか、旨い、美味しいと言われるものはクオリティの高いものから中央に行ってしまう。値段にはプレミアムがついてしまう。いいものは高くても売れるというのは資本主義社会としてあたりまえのことだし、それに価値を見いだす人がいる以上その現象を否定するつもりもないけれど、地の利ということがないとその土地は報われない。その土地に足を運んでこそ、得られる、経験できるもの。そういうコトやモノがもっともっとたくさん地方にキープできればよいなと思う。それでこそ地産地消ブームが本物になる。
というわけで、また獺祭を飲みに(もちろん文楽も観に)来年の夏来たい。
◎追記
獺祭は、かわうその祭りと書く。かわうそは、摑まえた魚を川岸にずらりと並べる習性があり、獺祭というのはこのことを指す。私がこの興味深い話を知ったのは向田邦子さんの名著「かわうそ」というエッセイによってである。この短編は何度読んでも、圧倒され、恐ろしく、心に刺のようにささって、まさしく向田邦子さんを代表する名作だと思う。

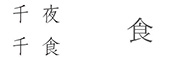




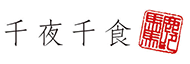
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真5-225x300.jpg)
![th_写真[トップ]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真トップ-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真2-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真3-300x225.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真4-300x225.jpg)