六本木「龍吟」
あれから、またどれくらい進化しているのか。
三年ぶりの名店訪問に期待値があがる。
しかも、待合では度肝を抜かれる演出?もあった。
三年ほど前に一度伺って、シェフの独特のセンスと大胆なプレゼンテーションに驚かされた。以来、なかなか機会を作れなかったのだが、ついに松山倶楽部で実現した。
予約の際に、二階に待合ができていることを聞いたので、友人とはそちらで待ち合わせることにした。先に着いたので、二階に通されお茶を飲んでいたときのことである。入って左手奥にはカウンターがあり、その後のガラスケースにはミミズクの剥製が飾ってあった。広い待合空間には私ひとり。と、ところが、何かがその空間の中で突然動いたのである。何がって、その剥製がである。手に持った湯のみを取り落としそうになり、腰が抜けそうになるほど驚いたのなんのって!!
それは、生きているミミズクだったのである。
思わず、立って近づいてみた。猫のようなまん丸い可愛らしいお目目。すると、今度はいきなり首を180°回転させるのである。エクソシストである。ミミズクは正面から見ると実に愛らしい顔をしているが、横から見るときわめて獰猛、さすがは猛禽類という面構えである。そして端っこにはもう一羽のミミズクが。聞けば、このカウンターのガラスケースの中で飼っているのだそうだ。度肝を抜かれるというのはまさしくこのことだ。まもなくやってきた友人も同じように腰を抜かしていた。
茶事では待合の床に掛けられている軸でその日の趣向をなんとなく推し量る。ミミズクは一体何を暗示するのだろう。ミミズク衝撃の余韻を引きずりながら、いよいよ席入りである。
店内は、満席である。空間の中ほど、全体が見渡せる気持ちのよい席に案内された。まずは、グラスシャンパンで乾杯。友人はランチの量を半分に調整して来たという。私も朝から何も食べていないので、おなかがぐーぐー言っている。ビルカール・サルモンの2004年が空腹の身体を駆け巡っていくのがわかる。
一品目の前菜は、貝尽くし。みる貝やとり貝、ホッキなどの貝類に酢橘をたっぷり絞って。何気なく出されるのだが、ひとつひとつの素材の火入れや炙り方を変えているので、素材によって食感も温度も違う。初っ端から何これ?と顔を見合わせる出来栄えなのである。また、この藍と金彩の伊万里の皿が独特というか、悪趣味ギリギリのところで踏みとどまっている。素晴らしいファーストインプレッションだ。二品目は雲丹のジュレがけ茶碗蒸し。からすみがふんだんにかけられ、小さな山芋、エディブルフラワーが散らされている。雲丹のこっくりした味わいが後を引く旨さ。うつわは、さすがに龍吟というだけあって、龍の胴が大胆に描かれている。お椀はオーソドックスに鱧。かなり立派な大きさで、脂がしっかりのっている。このお出汁に浮いている脂を見よ。さりげなく蓴菜も浮かんでおり、この味もさすがとしか言いようがない。
お造りは備前の陶板に乗った土ものの小皿尽くしでサーブされる。海の幸七皿の盛り合わせ。手前下からアワビ、アオリイカ海苔添え、ぼたん海老、カツオ、真子鰈、あん肝、そして真ん中には毛蟹をアワビの肝で和えたもの。どの順番で食べるか迷ってしまうのだが、迷った果てにどう食べたっていいのだわと気づき、アワビから時計回りに片付けていく。七皿すべてに違う薬味を厳選し、味の変化もきちんと計算されており、シェフの心意気がありありと伝わり、日本酒が進んでしかたがない。讃岐の凱陣、磯自慢、而今。どれも大純吟クラスの名品揃いである。続いての小皿、手前はホタルイカにスナップエンドウ、向こうは無花果の下にフォワグラが隠れている。焼き物は、ぷりぷりの黒ムツ。この火加減は絶妙。大根おろしにも、向こう側のバジル風味のおからにも合うように考えられている。どういう発想でこういう取り合わせになるんだろうね。シェフのアタマの中をのぞいてみたくなる。そして、メインは阿蘇の赤牛フィレの炭火すき焼き仕立て。このコロッケのようなものの中身は半熟の玉子なのである。これを赤牛にからめていただくという趣向。アイデアが楽しく、にんまりしてしまう。気の利いたサプライズですな。そして、シメはからすみ茶漬け。ほんま、たまりませんな。
デザートは名物マンゴー飴である。最初凍った状態で出され、この上にマンゴーのあったかい果肉を載せる。すると写真のような具合になる。まわりのマンゴーアイスは、ほとんどパウダー状である。そしてもう一品。瑞穂の国のデザートであるということをしっかりと意識したプレゼンテーション。お酒のスフレとソフトクリーム。熱燗と冷酒に見立てている。最後の最後まで、意外性と創造性を追求した一品を出してくる。最後はお薄でフィニッシュ。このきめ細かな泡を見よ。こういう状態に点てるにはそれなりの技術がいる。新しい茶筅を使わないとこうはいかない。
龍吟という名前のごとく、店内のインテリアもうつわにも、徹底的に「龍」が現れる。この執拗なまでの徹底は、料理にも当然の如く向けられており、ミミズクの暗示は徹頭徹尾のサプライス仕立てということであろうか。オーソドックスだったのは鱧のお椀ぐらいで、後は意外性の連続だった。素材と素材の組み合わせ方、調理の多様性、味の奥行きの計算、盛り付けのセンス。どれをとっても、強烈なオリジナリティが迸っている。いささかツーマッチ気味のひと皿もないわけではないが、それでもシェフの気概とチャレンジし続ける精神が和食をエンターテイメントに変えている。未知と既知をまたいで、和とかフレンチとかの領域を超え創発し続けている姿勢がある限り、彼はまだまだ進化し続けるのだろう。年に一度くらいは、その進化を楽しみに通いたい店である。ミミズクにも逢いに行きたいし。

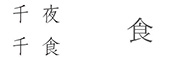




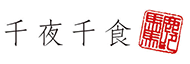
![th_写真[14]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真144-225x300.jpg)
![th_写真[16]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真162-225x300.jpg)
![th_写真[17]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真172-225x300.jpg)
![th_写真[18]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真182-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真59-225x300.jpg)
![th_写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真87-225x300.jpg)
![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真127-225x300.jpg)
![th_写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真128-225x300.jpg)
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真108-225x300.jpg)
![th_写真[11]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真1111-225x300.jpg)
![th_写真[13]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真135-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真313-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真48-225x300.jpg)
![th_写真[15]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真154-225x300.jpg)
![th_写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真97-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真68-225x300.jpg)
![th_写真[7]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/11/th_写真78-225x300.jpg)