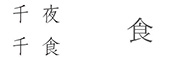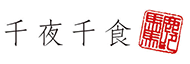台湾九份「九份茶坊」
高台にある茶藝館のテラスで
阿里山金萱茶のほのかな回甘(フェイカン)に酔いながら
赤いランタンが醸し出す妖しい世界にくらくらする。
どちらかと言うと日本茶派だ。普段飲んでいるペットボトルは「綾鷹」か「伊右衛門」、あるいは「生茶」。週末に淹れるのは一保堂の「芳泉」という煎茶で、時間に余裕があれば玉露を楽しんだりもする。「鶴齢」とか太っ腹の時は「天下一」(めったに買えないけど)だ。もちろん、抹茶も気が向けば点てることもある。これもだいたいは一保堂で煎茶と一緒に買う。お茶の先生が稽古場で使っているのは、三丘園の「豊昔」。紅茶は、「マルコポーロ」というのを缶で買っているが、あまり飲まないので、たいていそのまま古くなってしまう。中国茶は今となっては皆無である。
いや、20年ほど前一度だけハマったことがある。大昔上海に行ったとき、江蘇省宜興(ぎこう)で作られる紫砂茶壺がどうしてもほしくていくつか買ってきたことはある。紫砂茶壺とは江蘇省で採れる土(これを紫砂という)を使った茶器で、独特の色をしている。が、このときも、茶というよりは茶器にハマっただけで、買った当初は珍しさも手伝い烏龍茶などを淹れてはみたものの、結局使いこなせず、ほとんど茶を淹れることもなく茶壺はキャビネットの中に鎮座している。
だから、台湾といえば台湾茶と聞いても、ふーんという感じであった。それがである。九份を訪れ、むくむくと台湾茶への興味が再燃してきたのである。
九份は台北を訪れる観光客の定番人気となっている観光地だ。台湾北部の山間にあり、日本統治時代には金鉱山として栄華を極めたらしいが、やがて金や石炭の生産量が減り続け、1971年には閉山、しばらく衰退の時代があったという。それが1989年に侯孝賢監督の映画「非情都市」のロケ地となったことで再び注目されるようになり、さらに宮崎駿監督の映画「千と千尋の神隠し」はこの地で着想を得たという噂(スタジオジブリは公式に否定しているらしい・・)が広まって、台湾人だけでなく日本人にも人気の場所となっている。
瑞芳(前夜参照)からタクシーに乗り10分ほど。ここだと降ろされた場所から少し歩くと急勾配の細い階段があった。たしかガイドブックではもっと緩やかな道が紹介されていたはずと思うが、しんどい思いをして登ればそれはそれでお楽しみも待っているだろう。しかし、階段を登り続けるなんて普段あまりしないので、途中何度も休憩してしまう。ひーひー言いながらやっと提灯が連なる小径に出た。
狭い階段に赤い提灯を掲げた店が軒を連ねた独特の景観である。レトロというのか、異次元というのか。たしかに「千と千尋の神隠し」を彷彿とさせる空間が広がっている。下世話なのに、幻想的。猥雑なのに、神秘的。これは、マニア(何の?)にはたまらないだろうな。ここは夜景が素晴らしいのだそうである。提灯に明かりが灯されるまでにはまだ少し時間がある。うろうろしていて気になる茶藝館を見つけた。「九份茶坊」というのであるが、外に並んでいる人がいるくらい繁盛している。インテリアもかなり洗練されていて、ここで夕刻まで過ごすことにする。
どうせなら夜景が見えるテラス席をとリクエストする。席があくまで中をいろいろ見せてもらうことにした。入り口はお茶や茶器を売っている販売コーナーで、整然とセンス良く茶葉が並んでいる。奥は喫茶空間になっていて、階段を下りていくとギャラリーのように茶器がずらりと展示してあり、その奥でもお茶が飲める。左奥には作家ものの茶器などを販売する本格的なギャラリーもある。うーん。ここ凄いなと心のなかでつぶやきながら、テラス席に着いた。
注文を聞きに来たのでメニューを見せてもらい、阿里山の金萱というお茶にした。金萱茶は何度か飲んだことがあり親しみがあったのと本物のミルクのような香りを試してみたかったからである。やがて白い茶器が盆の上に乗せられ運ばれてきた。茶葉はくるくると丸まっている。茶葉を入れた急須へ目の前でシュンシュンと湯気を立てている薬缶から熱湯を注ぐ。待つこと1分。湯のみに注がれた水色は、淡い黄色である。ふわっと柔らかな香りが立ち上ってきた。そっと口をつける。やさしくほのかなミルクの香りと、ほんのりとした甘みの後に、柔らかいのにぐーっと奥行きのある滋味が舌に残る。これはうまいわ。上手く淹れられた玉露にも引けを取らない美味しさである。しかも、三煎でも四煎でも楽しめるという。一緒にやってきたのはこちらのオリジナルのパイナップルケーキ。今まで食べた(と言っても全て台湾土産で食べたものだけど)もので旨いというのに出会ったことがなかったので、これにもびっくりした。
パイナップルケーキをつまんで、二煎、三煎めをゆっくりと楽しむ。金萱茶の香りは少しずつ薄まっては行くのだが、独特のミルクのような甘い香りは鼻腔にまとわりついている。これ、「回甘(フェイカン)」と呼ぶらしく、厳密には舌の付け根に残る香りの余韻を言う。阿里山は台湾の中部にある高山で、阿里山金萱茶は土の質がよく一日の最高気温と最低気温の差が大きい海抜1500メートルくらいのところで栽培されているため、甘味を含んだ強い清涼感が茶葉にしっかりと凝縮されるのだそうだ。こういうのを清香というのだろうか。文字通り、清々しい気持ちになる。
やがて、少しずつ日が傾き、テラスから見えるすぐ下の坂にある茶藝館の提灯(ランタンと言うべきか)が灯り始めると、あたりは一瞬にして幻想的で妖しい雰囲気に満たされる。この赤い色にやられるんだな、みんなきっと。一度しか観たことがないけれど、たしか「千と千尋の神隠し」の映像もどこか奇々怪々な異次元の象徴として赤い灯りを効果的に使っていたのではないか。みな、その残像を現実の九份という町に重ね、そこにある赤い灯とともにそのイメージを脳裏で増幅させているのだろう。たしかにここは人を呼び寄せてしまう隠微な魅惑に満ちている。
◎追記
金萱茶も素晴らしかったが、茶器があまりによくできていたので、さっそくワンセット買って帰った。木の盆まで一式同じものを買ったので、後は淹れ方の技術だけであるが、中国茶は日本茶ほど温度に厳密ではないし、茶碗に注ぐ頃にはほどよい温度になっているので、まあ初心者でも手軽である。茶葉は、台北の王徳傳という店で見つけた。阿里山金萱茶はさすがにそんなに安くはないが、「九份茶房」を再現するために、小さな缶を買って帰った。こちらの店は赤い茶缶が目印で、その色に惹かれてつい入ってしまい、ああそうか、まだアタマの中にあの赤いランタンが灯っているのかと納得してしまった。赤い残像のインパクトはあまりにも強い。