南森町の割烹「宮本」
床の間とうつわと素材の三位一体で
暑苦しい大阪の夏を涼しく感じさせるのだから
まったくもって日本料理って凄い。いや、この店も。
大阪の夏は暑い、暑すぎる。汗だくになって暖簾をくぐる。カウンターの背には床の間がある。掛かっているお軸は、滝。それだけですーっと汗がひくような気がするのだから、まったくもって和の室礼というのは凄いと思う。わずかな空間が演出する季節の涼。そこにある主題を読み解き、季節に重ね合わせ、その日の趣向を推し量る。こんな芸当、日本人にしかできないであろう。
お軸で涼しい気分になったところで、涼感たっぷりの先付けの登場である。ガラスのお皿には、雲丹と夏野菜のゼリー寄せ。雲丹というのはそのままでも、冷たくしても、あっためても、炊いても、焼いても、煮ても、食える奴。素材としての軸がしっかりあるから、どう扱われてもその存在感はそこなわれない。たいした奴である。お椀はいつものお出汁と違って、はまぐりのお汁。こくのある海のエキスがたっぷり。シンプルに三つ葉だけというのがまたよい。お造りは城下鰈、ハリイカ、まぐろ。金彩を施した切子のうつわが素晴らしい。目に涼しく、気持ちにゴージャス。和食というもの、ほんとうに四季折々のうつわで楽しませてくれる。「滝」というお題が、ちゃんと素材とうつわに連なっている。そして夏といえば、鮎。清流を泳いでいたカタチにちゃんと焼かれ、芭蕉をイメージした葉ののうつわに盛られている。蓼酢でいただく季節の味わい。みずみずしい苦味を楽しむ。意表を突かれたのは毛蟹のお鮨。関西で蟹といえば断然冬のずわい蟹だが、夏の毛蟹はやはり旬であるから外せないのであろう。この漆のうつわがまた素晴らしい。漆黒に朱赤。真ん中にこんな小さな一品をぽんと置くだけで、目にも綾なご馳走が完成する。冬瓜のすり流しでちょっと一休み。いよいよ八寸である。視覚の記憶にさきほどのうつわの朱赤がくっきりと残った状態で、今度はほおずきの赤が連打される。鮮やかで、涼やか。表面にはていねいに霧が吹かれている。もうこれだけでご馳走であるのに、ひとつひとつのほおずきの中には、クラゲの酢の物や鱧の子の卵とじ、焼き茄子と海老の和えものがそれぞれ入っているのである。ガラス器のなかには、タコとそうめん南京とオクラの酢の物。自然のカタチも和食では季節を映すうつわになるのだと感嘆。いよいよ〆であるが、ここで関西の夏のもうひとつの代表選手の登場である。そう、鱧だ。クレソンと一緒に鍋仕立てにしていただく。鱧は出汁にくぐらせると歯ごたえに凄みが出る。お出汁と一緒に熱々をいただく。デザートはフルーツのジュレと、ふるふるのわらび餅。最後に小さなお茶碗でお薄が出る。すべていただいた頃には、汗もすっかりひいてゆったりした心地になっている。
「夏はいかにも涼しきように」
利休七則のひとつであるが、昨今のたとえようもない激しい暑さに参っている気持ちが、こちらのカウンターに座り料理をいただいているだけで癒やされた。このまま襖を引くと、よく冷えた隣のお座敷に布団が敷いてあって、そこでうたた寝・・・そんな妄想が頭をよぎった。それがやりたきゃ、旅館に泊まらなきゃ・笑。

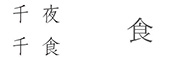




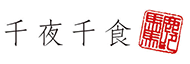

![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真14-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真23-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真33-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真42-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真52-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真62-225x300.jpg)
![th_写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真81-225x300.jpg)
![th_写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真9-225x300.jpg)
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真10-225x300.jpg)
![th_写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真121-225x300.jpg)