2014-08
更紗制作・石田加奈さん
加奈さんはインドネシアではガイジンである。そのガイジンがジャワ島で失われつつある伝統的なジャワ更紗(バティック)を作り続けている。更紗は、ため息が出るほど美しく、震えるほどに精緻なかたちを表現していて、現地でbatik isisと呼ばれセレブリティの奥様方にたいそう人気なのだという。
京都麩屋町にある加奈さんのお店「isis」の名は前から知っていた。「isis」にはジャワの古い言葉で川辺に吹く涼しい風という意味がある。加奈さんはイシス編集学校の関西支所「奇内花伝組」の先輩でもあり、イシス編集学校の編集術ワークショップ「浪花参座」でイシスの意味を説明するときに必ず紹介していたからだ。加奈さんとは去年の夏、函館で開催された「未詳倶楽部」ではじめてお会いした。おっとり柔らかな京都弁で話し、独特のエキゾチックな雰囲気をふわっとシュガーコーティングしたようなチャーミングな女性である。batik isisの生地で作ったと思われる素敵なブラウスやワンピースをお召しになっていた。
そのbatik isisが豪徳寺イシスの本楼にやってきた。その数100枚以上。東さん率いるHIGASHI-GUMIの手になる空間のしつらえは壮観である。圧巻である。絶景でもある。
![写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真210-300x225.jpg)
![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真18-300x225.jpg)
加奈さんの工房があるのはジャワ島チレボン。ここに一年のうち数ヶ月滞在し現地の職人たちと更紗づくりをしている。ジャワ島でも近代化の波は押し寄せていて、今や伝統的なジャワ更紗も絶滅の危機にある。加奈さんは昔ながらの伝統的な技術や文様を復活させることに力を注ぎつつ、日本感覚を活かした図案や色彩のアイデアも出しながら、独特のクオリティの高いbatik isisを作っている。完成までに一年かかるという手描きの更紗は一枚一枚がオリジナルで同じものはない。
加奈さんが凄いのはそのオリジナルを保存しようとか一切考えていないことである。更紗の型を残しておけばそれはやがて膨大な財産になるはずなのだが、そういう気がない。今やbatik isisはインドネシアでは高級ブランドとして認知されている。オリジナルものには更紗の端にisisというロゴが入っており、これがないと満足しないという顧客もいると聞く。
この姿勢はなんだろう。
加奈さんに「それはとてももったいないことですやん」と問うても、「そんなんあんまり関係ないことやし、興味ないし」とやんわりかわされてしまう。美しいものを作っている人は、その美しさに無頓着なのだろうか。美しさというものは儚さと表裏一体なのだろうか。
沖縄の首里織。読谷山の花織。喜如嘉の芭蕉布。太平洋戦争でほとんどの技術が途絶えかけたとき、現地に出向き古布を蒐集し調査研究をすることで沖縄の染織を蘇らせようとした人々がいた。中心となったのは民藝運動の祖・柳宗悦である。民藝運動に加わった人たちは、積極的に沖縄に学んだ。現地の人たちに聞き取り調査をした「沖縄織物の研究」は今も沖縄織物研究のバイブルである。芭蕉布の人間国宝平良俊子さんは倉敷で大原總一郎や外村吉之助に出逢わなかったら誕生しなかっただろう。芹沢銈介も細々と残っていた紅型を学ばなければ、型絵染めで人間国宝になっていなかったかもしれない。沖縄の染織が人を感動させるような美しさをもっていなければ、絶えていたかもしれないと想像してみれば、美しいものは必ず誰かの手によって必ず蘇る。
加奈さんのつくるジャワ更紗もそういうことかもしれないと思う。もちろん、batik isisは現地でセレブリティの方々を中心にとても人気があるというし、職人たちもしっかり育っているようだし、技術そのものは途絶えることはないだろう。そうしたら、柄だって決して失われるようなこともないだろう。
![写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/121-e1407044762242-225x300.jpg)
![写真[11]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/111-e1407044793271-225x300.jpg)
![写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/91-e1407044838780-225x300.jpg)
![写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/101-e1407044861745-225x300.jpg)
たぶんそういう無心さを持つものだけが、美しいものを生み出すことができるのかもしれない。柳宗悦も言っている。「名無き工人によって作られた下手のものに醜いものは甚だ少ない。そこには殆ど作為の傷がない。自然であり無心であり自由である」と。ひとつだけ訂正しておこう。加奈さんの更紗は下手ではない。限りなく上手ものではあるけれど。
◎追記
本楼で素晴らしいbatik isisを見ながら、どの更紗を買おうかとずっと迷っていた。かねてから更紗の布で帯を仕立てたいという野望を抱いており、今回は帯にしても映えるようなものを探すつもりだったから。あれこれ悩んだ末に、ファーストインプレッションで「あれだ」と感じたものを選んだ。さっそく呉服屋さんに相談した。もともと帯のためにつくられている布ではないので、後ろのお太鼓の部分と正面にどんな風に柄を配置するかで何度かやりとりをし、帯を結ぶとき手先を左右どちらでしているかの確認もし(端の柄をちゃんと配置するため)、三ヶ月ほどしてやっと出来上がってきた。裏は濃紺の綿地なので、盛夏以外締められる素敵な帯になった。どんなきものに合わせようかわくわくしている。
とりあえず無地のきもの中心にいくつか置いてみたが、どんなきものにも合う。ジャワ更紗がすでに日本的感性にすっかりなじんでいるという証拠だろう。
韓国街の「ソルロンタン」
韓国料理などめったに食べないのに、新年はじめての食事でなんとNYのコリアンタウンに出向くことになった。滞在していたNoMad Hotelのニューイヤーズイブパーティーが終わったのが午前2時半頃。シャンパンを浴びるほど飲んで年甲斐もなく踊ったりしたので、微妙に空腹である。NYに住む友人がコリアンタウンに行って「ソルロンタン」を食べようと誘う。なんだか楽しい響きである。それ何?と聞くと、白いスープの中にごはんと麺が入っているという。え?実は同じ皿や丼に形の違う炭水化物が入っていると、途端に食欲を失いどんなに美味しいと言われようと食べられなくなってしまうのである。かちんうどん。うどん入りおじや。そばめし。焼きそば定食も、ラーメンライスも、同時には食べられない。でも、ま、スープだけ飲むという選択もあるか。小腹も空いているし、ラーメンほどカロリーもなさそうだし。さっそく、コリアンタウンへと足を伸ばした。
NoMad Hotelはブロードウェイ28丁目。コリアンタウンまでは4ブロックだ。歩いて5分とかからない。それにしてもこのエリアに足を踏み入れるのは何年ぶりだろう。3時近いのに目的の店は煌煌と発光している。どうやら客もいっぱいのようだ。肉の焼ける香ばしい匂いも立ちこめている。
愕然としたのはその店がなんとあのホテルの中にあったことだ。嘘でしょ。
NYに通いだした二十数年前。まだHISが秀インターナショナルと呼ばれていた頃に、エアー&ホテルという格安チケットを買ったことがある。そのときのホテルがここだった。当時の32丁目ブロードウェイ界隈というのは、庶民的といえば聞こえはいいが、はっきり言ってあまり治安がよろしいとはいえないエリアだった。まだ韓流の兆しもないような時代だったから、単身コリアンタウンに泊まるというのは無謀とも言えた。案の定、たぶん韓国から来たであろう男の子のグループに目をつけられ、深夜に部屋のドアをノックされたり、電話をかけてきてからかわれたりした。こんなホテルに泊まっておられるものか!怒り心頭に達した私は、翌日即座にチェックアウトし、他のホテルに移った。そもそも外出から帰ってフロントに部屋番号を告げると、こちらの名前を確認せずにキーを渡すような不用心さがあった。この体験は、後に泊まるホテルにこだわるようになるきっかけともなったのだった。一人旅のニューヨークでいちばん大事なのは、一に安全、二に安全。その怖くて嫌な思いをしたホテルの名前を忘れるはずがない。煌煌と輝くホテルのネオンを見て、瞬時のうちにそのときの記憶がよみがえってきた。
二十年の歳月を経て、なんと変わったものだろう。リノベーションは、NYホテルの常ではあるが、それにしても、だ。コリアンタウンそのものも、ソウルの明洞(ミョンドン)や狎鴎亭(アックジョン)と見まごうばかりで、すっかりエッジーな雰囲気になっている。日韓首脳同士が緊迫した関係にある時期なので、ほぼ満員の店内で日本語で会話するのは妙に憚られた。(あかん、日本語しゃべったら追い出される〜、などと交わすブラックジョークは楽しいのだが)
さて、「ソルロンタン」である。


「ソルロンタン」は、牛の肉や骨を長時間コトコト煮込んでつくるスープ。骨髄まで煮出すのでエキスがたっぷりで白濁している。この店では、米と麺が一緒に入っている。ごはん抜きにできるというので、私は麺だけにしてもらった。白濁しているスープを見ると反射的に博多系豚骨スープを連想してしまうが、かなりあっさりしている。というかいわゆる「うまみ」というものが感じられない平坦な味である。調べてみたところ、調理時にはほとんど味付けせず、好みで塩コショウ、唐辛子などを入れ食べるものらしい。キムチなどを入れてもいいのだという。つまるところ、豚骨ラーメンに紅ショウガを入れるような感覚かしらと思う。
まずは、軽く塩胡椒を振ってみる。とたんに白濁しているスープがくっきりと際立つ。次に刻んだ葱をたっぷりのせる。ここまでは想定内の味だ。そして、こわごわとキムチを入れる。唐辛子の赤がスープに溶け出し、妙に食欲をそそる風情になっているではないか。酸味が加わると、味にぐんと奥行きが出るような気がする。うん、これ悪くない。
ソルロンタンにキムチ。豚骨スープに紅ショウガ。
微妙な味や調理法は違うにしても、かの国と日本、似て非なるのではなく、こんな白いスープさえも非ではあるがどこかやっぱり似ているのだ。
かつて大陸からの文化を伝えてもらった中継地であり、朝鮮からも多くの恩恵を受けてきた私たちの国日本。隣国として、文化を伝えてもらった国として、本質的なところの相互理解と違いをしっかり認め合うことは必要だし、そのコミュニケーションにはさまざまな方法があるはずだ。スパイス次第でいかようにも味を変える「ソルロンタン」を啜りながら、日韓のAIDAに思いを巡らせた元旦だった。
NYフレンチ「ダニエル」
年に一度の年末NY。彼の地に住む友人たちが滞在中一度はスペシャルディナーにつきあってくれる。今回は「ダニエル」である。毎回、予約しようとするのだが、なかなかほどよい時間に予約が取れず、ここはずーっとお預けになっていた。76丁目にある「カフェ・ブリュー」は何度かは行ったが、やはり本家本元に来なくては話にならない。
今年は7時というディナーとしては理想的な時間に予約が取れた。友人たちとは現地集合である。こちらのレストランのほとんどにウェイティング・バーがあるので、先に到着したものから適当にシャンパンとかを飲んで待てるので便利なのである。オンタイムにタクシーを降りると雪が舞っていた。おお寒。いくらダウンを着ているとはいえ、中は薄いシルクのワンピース一枚。だが、さすがに冬のニューヨークの室内はあったかく、肩を出したドレスでも寒くないよう空調は完璧にコントロールされている。ちょうど友人と入り口で出会ったので、もう一人が来るまでにワインリストを見せてもらいシャンパンを選ぶ。メニューの分厚いこと。バーはバーで素敵なので最初のシャンパンはこちらで楽しむことにした。ほどなくもう一人の友人登場。全員そろったところで乾杯をし、しばし歓談。
やがてダイニングルーム中程の全体が見渡せるなかなかいい席に案内される。大好きなハイバックソファ席。メニューを見ながら、どのコースにするかで思いっきり迷う。いろんな料理を少しづつ7皿で供するテイスティングメニューというのがあり、せっかくなのでそれにした。オプションでその皿に合うワインをセレクトしてくれるワイン・ペアリングというのも一緒に注文する。これ、ここ最近のトレンドで、料理に合わせて最適のワインをグラスで持ってきてくれる。店側都合でもあるだろうが、ボトル選びに失敗するリスクを思えば客側にとっても都合のよいシステムだとは思う。ワイン好きの人にとっては邪道なのかもしれないが、私はいろんなのを少しずつというのも決して嫌いではない。
店内のライトがとても暗いので写真のクオリティはあまりよくないのが残念だし、ひとつひとつのメニューをちゃんと記録していなかったので、料理の細かい説明は割愛させていただく。が、全7皿の流れにちゃんと起伏が仕込まれており、ブロック状になったテリーヌ仕立ての一皿やスープ仕立ての一皿に歓声をあげ、メインの子羊にいたるまで幾度もの嬉しい驚きがある。テイスティングワインをセットしたせいでワインもデザートワインを含め6種類もサーブされ、おなかはパンパンである。それでもデザートの最後に出てくるふわふわの焼きたてマドレーヌまでしっかりといただき、大満足かつ大満腹の夜となった。
トータルな印象としてはさすがに三ツ星。接客も、インテリアの雰囲気も、料理の内容も申し分はない。サービスする人の動きには無駄がなくエレガントだし、モダンテイストなバーからダイニングルームに入ると、一転してコンサバティブで優雅なインテリアが迎えてくれ、こういう雰囲気はやはり日本ではなかなか真似の出来ないレベルである。価格も日本の三ツ星フレンチと比べると(チップを勘定に入れなければ)、3コースで125ドル、7コースで220ドルと意外に良心的に感じるほどである。
ただ私が終始考えていたのは、もはや日本のフレンチを始めとするレストランのクオリティの高さは、いまや世界で引けをとらないレベルに来ているなということだった。東京は世界でいちばん三ツ星レストランの多い都市なのである。10年前に来ていたらすっかり魅せられ大感激していたであろうが、今やわざわざダニエルに来なくても東京でもこのクラスのレストランはたくさんあるという事実の方にいたく感じ入ってしまったのである。
ひとつだけダニエルに優位性があるとすれば、それはやはり何と言ってもここが大好きなニューヨークにあるということである。雪が舞うマディソン・アベニューを歩きながら、65丁目を曲がり、ダニエルを目指す。正面に立つと、ドアマンが扉を開けてくれる。中に入るとクロークが素早くコートを預かってくれる、バーに案内される。完璧なレディ扱い。この女心をときめかせてくれるきわめてドラマティックな一連の流れだけは、東京にはない。
鳶職人・多湖弘明氏
鳶職と聞いてどんなイメージを思い浮かべるだろうか。
建設現場の足場を組んで高いところで作業する人。派手なニッカボッカみたいな作業着を着ている人。最近の言葉で言えばガテン系。古いところでは新門辰五郎(ほんまに古い)が鳶の親方だったことは知っている。それくらいしか思いつかなかった。しかも、直前にアマゾンで購入した「鳶」を東京に持っていくのを忘れてしまい、予備知識も一切ない。事前情報は、そ乃香こと和泉さんからの「凄い人なんですよ」という言葉のみ。ままよ。当日のセレンディピティに期待しつつ豪徳寺に向かった。
今回はカウンターに入り飲み物を配るお手伝いをすることになっていたので正午には会場に着いた。カウンターの中で飲み物のチェックなどをしていたら、本楼ではえらい小粋な出で立ちの見知らぬ男性がすでにマイクテストをしていた。リハーサルの設営の人か、音響のチェックをする人なのか。いや、その人が今回のゲスト多湖弘明さんだったのだ。笑顔がとても素敵なイケメンくん。鳶職人だなんてとうてい想像できない雰囲気をまとっている。だけど、キリリと引き締まったお顔は、何かにいつもチャレンジし続けている人だけが持つオーラを放っていた。
いよいよトークが始まった。
多湖さんはマシンガントークで淀みなくしゃべる。大阪市西成区生まれ。15歳の時、大阪の梅田スカイビルのリフトアップ工事を間近で見て度肝を抜かれ、建築を仕事にすることを意識するようになったという。このビルができたときの仰天は私もよく覚えている。二棟の高層ビルが途中で斜めの階段でつながり、てっぺんには空中庭園がある。大阪らしいド派手かつ奇想天外な設計なのだが、その工法もきわめてユニークで少年の多湖さんが見たのは地上で組み立てられた連結部分の空中庭園をリフトアップ工法によって最頂部まで引き上げているそのシーンである。その少年の日の強烈な印象が今の多湖さんの立ち位置を決めたともいえる。
![写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真2-300x225.jpg)
高校を卒業してすぐに交通事故に遭い、半身不随になるかもしれない大怪我から復活。リハビリ感覚でアルバイトした建設現場での仕事が多湖さんの未来を決定づけた。大阪で最大手の鳶の会社で、超大型現場に関わり、一年後に移った会社でも「大阪ドーム」の仕事を経験。さらには一緒に現場で仕事している人があの梅田スカイビルの工事をしたということも知り、多湖さんは鳶の仕事に夢中になった。
その後一年ほどニッカボッカ姿で世界を旅して、バルセロナのサグラダ・ファミリアの現場を訪れたりもしたという。帰国し再び鳶の仕事をしているときに、東京に第二の電波塔が建つことを知り、世界一の建造物に携わりたいと上京。むろん、あてはなかった。だが、そこは彼一流のやり方で、東京スカイツリーの建設現場に携わった鳶のひとりになったのである。
私をはじめ、参加者も、そしてたぶん松岡師匠をも唸らせたのは、多湖さんの目的に向かっていくパワーとその方法である。たとえば、いい建設現場を見つけるとそこへ出向き働きたいと懇願する。たいていは門前払いなのだが彼は早朝から現場の掃除を続け、信頼を得る。出入りを許された現場ではしっかりと働き成果を出す。この積み重ねで、東京スカイツリーのてっぺんまで行ったのである。今回、鳶の本を書くにあたっては、今まで本など読んだことがなかったので本を1000冊読むことを自分に課した。同じ小説家の本を何冊も読みその文体を真似ることもした。その結果、100%彼の文章である「鳶」が完成した。多湖さんの中では次の10年、20年の人生設計はもう立てられていて、そのためにも頭の中に浮かんだり、いろいろ考えていることを、すべて紙にアウトプットし尽くして部屋に貼る。実行したり、実現できたものを、マジックで消していく。そうやって目的を果たすためには何をすべきかを四六時中考えているのだという。
必然から生み出された独自の方法論。
松岡師匠の編集工学によく似たメソッドがそこにある。私たちが驚いたのはそれを彼が試行錯誤の末、ひとりで手に入れたこと。その点に尽きるのだ。
人間力。
多湖さんの話を聞いていて、そして懇親会で話をしながら感じていたのはまさしく「人間力」ということだった。大企業に属していようがいまいが、フリーランスであろうがなかろうが、結局人は自分というエンジンがその気になって動き出さなければ成長はできない。その気のないところにセレンディピティなんて決して起こらないだろうし、薫陶を受けさせてくれる人物だって現れない。ましてや生と死が紙一重の空中で働く鳶職人ともなれば、ありふれた日常が一瞬で変わることを熟知しているだろう。そのぎりぎりのところで日々を過ごしていれば、一日一日の重みはずいぶん違うはずだ。
![写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真3-224x300.jpg)
ところで冒頭新門辰五郎のことに触れたが、鳶の世界にはこの辰五郎の流れを組む火消しの名残のある「町鳶」とゼネコン工事現場で働く「野帳場鳶(のちょうばとび)」とがあるそうだ。もちろん多湖さんは後者の鳶で、専門工事業者としてゼネコンの下請けで仕事をする鳶を「組鳶」ともいうのだそうだ。辰五郎はたいそう肝が大きく、最後の日本の侠客ともいわれたらしい。徳川慶喜の警護をしたという話も有名である。火消しであり侠客でもあったその侠気(おとこぎ)を培ったのはやはり命をかけて働く鳶という仕事ではないか。そんな気がしてきた。
多湖さんが今回「鳶」を書いたのは、一緒に働いていた仲間が目の前で亡くなったことが直接のきっかけである。だが、命をかけて働く職人たちの生き様や鳶の世界のことをしっかり伝えることが、仲間とそして多湖さん自身が生きた証になる。そんなせつない思いもあるのだ。
本の最後にも書かれているが、多湖さんとメールをやりとりしたら、最後に「本日も、ご安全に!」としめくくられていた。その言葉の切実さは、私にもひしひしと伝わってきた。

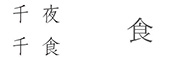






![写真[13]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/131-e1407044292512-225x300.jpg)
![写真[14]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/141-e1407044341729-225x300.jpg)
![写真[16]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/161-e1407044424450-225x300.jpg)
![写真[17]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/171-e1407044456373-225x300.jpg)
![写真[15]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/151-e1407044492946-225x300.jpg)


![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真11-300x225.jpg)
![写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真21-224x300.jpg)
![写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真31-225x300.jpg)
![写真[28]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真28-254x300.jpg)
![写真[29]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真29-231x300.jpg)
![写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/5-e1406976037692-225x300.jpg)
![写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真6-225x300.jpg)
![写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真8-225x300.jpg)
![写真[25]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真25-231x300.jpg)
![写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真10-225x300.jpg)
![写真[14]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/14-e1406976188296-225x300.jpg)
![写真[26]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真26-220x300.jpg)
![写真[27]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真27-243x300.jpg)
![写真[23]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真23-225x300.jpg)
![写真[22]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真22-225x300.jpg)
![写真[7]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真7-225x300.jpg)
![写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真9-225x300.jpg)
![写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真12-225x300.jpg)
![写真[15]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真15-225x300.jpg)
![写真[17]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真17-225x300.jpg)
![写真[20]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/20-e1406976406658-225x300.jpg)
![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/1-e1406891936922-225x300.jpg)