2015-02
オーベルジュ内子
オーベルジュ内子は、内子の町並みを見下ろせる丘の上に建っている。入り口は素っ気ないくらいのさりげなさで、そこがとてもいい。エントランスへと続く小道には、季節の草花が生い茂っている。ロビーは、木の香りが漂う、あたたかさに満ちた空間になっている。客室はわずか5室。全室離れで、部屋は広々としたスイートである。地元の和紙を障子やライトにあしらい、内子の伝統建築を模した「透き」をデザインしている。テレビも時計も、部屋にはない。リビングルームに面したテラスには夏の光が降り注ぎ、青々とした桜が濃い影を落とす。
オーベルジュというスタイルは日本でもすっかり定着したが、やはり魅力はその土地の食材を使った料理に尽きる。夕食はこちらで、とチェックインのとき案内されたダイニングルームは木とガラスをうまく組み合わせた開放感のある空間である。ひとふろ浴び、部屋でくつろいでいるうちに、夕食の時間になった。ダイニングルームの照明は落とされ、テーブルには和ろうそくが灯され、幻想的な雰囲気である。そう、ここ内子は木蝋で財をなした町なのである。和ろうそくはその木蝋からつくられる。インテリアの雰囲気づくりに、土地の名産品が貢献するなんて、しかもそれが和ろうそくだなんてなんと素敵なのだろう。灯りもどこか誇らしげに揺らいでいる。
内子産のワインがあるというので、まずはそれで乾杯する。内子夢ワイン。ピオーネやベリーA、ロザリオ、やまぶどうなどから、赤白ロゼを作っており、世界でいちばん小さなワイナリーなのだそうだ。軽く、爽やかなぶどうの香りがする。料理1品目は、内子豚で作った生ハム。パイナップルのサワークリームにいちじくが添えられている。山の湧き水を飲んで育つという内子豚は、柔らかな肉質で、しっとりした食感。花オクラのお皿には、宇和島御荘で穫れた岩牡蠣。赤ワインとエシャロットのソースがかけられている。こっくり豊かな味わいの牡蠣である。スープは夏らしくコンソメジュレ。中には隣町の五十崎の工房で作られているリコッタチーズ、フォワグラ、オクラが入っている。そして隣の市である大洲の肱川という鵜飼で有名な川の天然うなぎ。天然のうなぎなど、そうそう食べる機会はない。力強い歯ごたえと、滋味豊かな味わいに唸る。続いては媛っ子地鶏のソテー。これも愛媛県産のブランドである。伊予路軍鶏の血を引いているだけあって、ぷりぷりした歯ごたえが心地よい。口直しのシャーベットはこちらの特産品であるジャバラ(柑橘系の一種で、花粉症などの抑制に効果があるとして注目されている。独特の甘酸っぱさがおいしい)。メインは伊予牛ロースのソテー。言うまでもなく、旨い。しっかりした肉の味がする。デザートは茄子のコンポートである。茄子を赤ワインとシロップで煮ているのであるが、これもたいへんに美味であった。
契約農家から届くとれたての有機野菜。内子夢ワイン。内子豚。宇和島の岩牡蠣。五十崎のリコッタチーズ。肱川のうなぎ。媛っ子地鶏。伊予牛。ジャバラ。どれも内子に足を運ばなければ食べられない地元のものばかりである。志の高い生産者たちが、自然のままの栽培方法に真摯に取り組んで、そこで作られたきちんとしたものを地元のオーベルジュが料理という完成形にして出す。理にかなった素晴らしい循環である。こうした取り組みは今さまざまな地方で行われているけれど、ここ内子にはそのきわめて洗練されたひとつのスタイルがあると思う。地方の豊かさは、地方の底力でもある。内子の「身土不二」、それを味わいにまた訪れたい場所である。
愛媛内子「かわせみ」
4月に金毘羅歌舞伎を観に行ったときに、内子文楽の案内チラシを配っていた。土日開催なので、週末を利用すれば簡単に行けることに気づき早速チケットを申し込む。ついでに母と妹も誘い、家族旅行も兼ねることにした。金曜の夜から実家に帰り、当日の朝高松から松山行特急いしづちに乗る。途中の駅で妹とも合流し、一路松山へ。松山で特急宇和海に乗り継いで約30分。内子の駅はローカルにしては立派な駅舎である。駅前には文楽の幟がはためいている。
文楽の前にまず腹ごしらえである。タクシーで八日市護国の町並みへと向かう。ここは江戸時代には大洲と松山をつなぐ街道で、お遍路道や金毘羅参詣道をも兼ねていたという。江戸期には和紙、江戸後期から大正にかけては木蝋の生産で栄え、莫大な富を得た商人たちが建築に競って投資し、その町並みが今も残っているのである。江戸後期、明治、大正とそれぞれの時代の建造物が建ち並び、白壁と浅黄色の壁には大いなる時が刻まれている。海鼠壁(なまこかべ)、虫籠窓、うだつ、鏝絵(こてえ)、懸魚(けぎょ)など伝統的な造形美もそここに見られ、観光客相手の店もあるにはあるがさりげなく古い町並みにとけこんでいる。
めざす店は、その通りの中ほどにある浅黄色壁の古民家。やきものや民芸が好きなのだろうことは、置いてある本や調度品を見ればすぐわかる。店内を見渡していたら、吉田文雀さんと竹本住大夫さんの揮毫を発見した。お店の人に尋ねると、最初文雀さんが書かれたものを飾っておいたら、それを見た住大夫さんが「わしも、書く」とおっしゃったのだそうだ。「寿」とある。おおらかで伸びやかな字に、お人柄が重なるような気がした。それにしても、はるばる文楽を観に来て、入った店が文楽の人たちが通っている場所だとはなんという偶然なのだろう。いや、これも必然として呼ばれたということなのだろうと思うことにする。僥倖である。
こちらの食事は昼も夜も予約制である。地元の朝市で売っている野菜、自家製のお味噌などを使った素朴な郷土料理というのを出す。うつわも昔はそうそうこんなお皿で食べたよねというような、なます皿や塗りのお椀。近くの川で穫れる鮎の塩焼きや紅しょうがの入ったお寿司、かぼちゃや山菜を炊いたもの、焼き茄子とオクラ。どれも、懐かしくなるようなにほんのお惣菜である。素性のちゃんとわかっている地元の食材を使い、きちんと丁寧に作ったものを食べる。こういうのこそが、今の時代にはひとつの贅沢なカタチではないかと思う。デザートは栗がゴロゴロ入ったきなこのアイスクリーム。これも懐かしい味がした。
知らない土地で出逢う食やモノ、そして人との交流がどれだけ旅を豊かにしてくれるだろう。文楽に興味を持たなければ内子という土地を訪れることはなかったかもしれない。旅というもの、何がきっかけになるかはわからない。だからいつもアンテナを全開にし、ぴん、と立てておかなければいけないのである。
京都祇園「千ひろ」
年がら年中賑わっている京都ではあるが、私が秘かにシーズンオフだと思っている季節がいくつかある。ひとつは、祇園祭が終わって五山の送り火が始まるまでのわずか二週間、もうひとつは紅葉が終わり年末にさしかかるやはり二週間ほど。兎にも角にも暑いのと、底意地が悪いとしか思えないほどの底冷えがするという、どちらも観光にはあまり適さない時期である。が、ちょっと歌舞伎を観に行って帰りにごはんを食べるとか、古門前や二条あたりで骨董屋をのぞきたいとか、寺町の三月書房でマニアックな本を探したいとか。この時期を選べば、道路は空いててタクシーはすいすい走るし、修学旅行生も集団の観光客もほとんどいないのである。せっかくの古都を楽しむのに、誰もわざわざこんな季節に来ようとは思わないのである。神戸から日帰りで行くには、それがちょうどよい。
この店に行くのはは、たいてい南座とセットになっている。歌舞伎が終わってから直行するというのが近頃のパターンで、ご主人も「観て来たんですか」といつも尋ねてくれる。で、猿之助(亀ちゃん)など観て来たと言おうものなら、その後いかに先代の猿之助が素晴らしかったかという話になる。なにしろ、祇園育ちのご主人である。子供の頃から歌舞伎を観ているので私なんぞとは年季が違うのである。京都が恐ろしいと思うのはこういうときである。たいていの祇園の店には、南座のポスターはむろん、芸妓さんや舞妓さんの千社札やうちわ、都をどりなどのポスターが必ず貼ってある。彼らにとっては、祇園のお茶屋も歌舞伎も日常なのであって、特別なものではない。代々続いている店に生まれたならば、子供のときから南座に連れて行かれるし、年頃になると祇園のお茶屋にも行くのであろう。歌舞伎の話ができてあたりまえの環境なのである。ほかの土地ではなかなかこうはいかないし、こればっかりはお金では買えない文化資産とでもいうものだろう。
さて、観光はシーズンオフではあるが、食材は旬のオンパレードである。
まずは蓴菜、雲丹、穴子、きぬさや、湯葉、パプリカ、椎茸のカクテルゼリー。こっそり入っている丸いのは、なんとデラウェアである。そう来たか、と唸る。フルーツをさりげなく忍ばせるというのはこの店のお家芸なのである。続いて、お盆に小皿を乗せた楽しいスタイル。左から時計回りに、鱧の子、鯛、松茸とおじゃこ、鯛の子のゼリー寄せ、枝豆のすり流し。これを肴にちびちびと日本酒を飲るのである。そして、鱧の造り。初めていただいたとき、鱧を刺身で食べられるなんてと感動したことはよく覚えている。関西でも鱧はやはり湯引きが定番で、刺身を出す店は少ない。ご主人が鱧の骨も一緒に細かく切る音を聞いていると、ああ千ひろの夏だなとしみじみ思う。骨切りされた刺身は、何ともいえない歯ごたえである。丸い輪っかは、鱧の浮き身である。コリコリしたグミのような質感だ。これもここで知った部位である。こちらの刺身は、お醤油でも、細かく刻んだ塩昆布でも食べられる。こういったスタイル、近頃ずいぶん多くなって入るが、こちらはこれが昔からの流儀である。お造り二品めは炙ったトロ。底にすった山芋が隠れてい、これにのりをはさんで一緒に食べるのが好きである。
真打ちのお椀は、まさしく季節の先取り。鱧と松茸である。この組み合わせ、昔は夏を惜しみながら、来る秋の豊穣を連想させたものだが、最近は松茸が早く出回っているのか、夏の盛りでも食べられるようになった。食いしん坊にとってはありがたいことである。焼物は鮎。いつも笹の葉を描いたこの皿で出される。右端に添えられたのは煮たバナナである(これもなかなか)。白いのは湯葉に絶妙な味わいの出汁を足し漉してとろとろにしたものである。で、この中には、桃が隠れている。桃のみずみずしい甘みと、まったりした湯葉の味わいが、ひとつに溶け合うセクシーさ。揚げ物は贅沢にも松茸のフライである。うん、松茸って何をされても、ちゃんとその存在感ある香りは失われないのね。すだちをキュッと絞って、さくさく食べる。そうしてまたまた焼物は琵琶湖の鱒である。希少な魚である。独特の香りはやはり京都人が愛する琵琶湖産ならではなのだろう。最後はこれも名物の焼きなすである。胡麻と海苔をたっぷりかけて。〆の食事は鮎ご飯と冷たいお味噌汁。本日も大満足。
鱧、松茸、鮎、鱒。鱧の子、鯛の子、雲丹。たまりませんなあ、この素材。シーズンオフの冥加である。
芦屋鮨「㐂一」
芦屋になかなかよい鮨があるらしい、と飲み友達のツネヒコ情報である。何でも、苦楽園の「まつもと」の弟さんが独立したというのだ。「まつもと」はかなり前に一度だけ伺ったことがある。凛としていて、エッジの効いたなかなかの鮨であった。店主が若かったことに驚いたのをよく覚えている。若いといっても30代ではあろうけど(こっちが歳とってくると30代でも若いと思うようになる)、面構えに非常にビシッとしたものを感じたものである。そのとき、弟さんは奥にいたのだろうか。あまり顔は覚えていない。が、ストイックに修行を重ねてきたのではないか、と思わせる店であったので、噂を聞いただけでうずうずしてきた。早速予約する。
場所は芦屋の打出と聞いた。ここはたいそう歴史の古い場所で、神功皇后の皇子たちが打ち出た場所であるとか、昔から交通の盛んな場所であったことから旧西国街道が初めて海に打ち出たところとか、はたまたすぐ近くに打出小槌町もあるので、例の打ち出の小槌に由来しているという説まである。近所には業平(なりひら)や公光(きんみつ)という地名もあって、こちらは伊勢物語に登場する在原業平やその物語に憧れた若者の名前がそのままついている。こういうことを語りだすと芦屋には、鵺塚(ぬえづか)とか親王塚、古墳まであり、とにかく古い場所であることがよくわかる。
目指す鮨は打出の駅よりは、芦屋駅に近かったが、公光町の隣の大桝町というところにある。現代的なビルの中に突如白木の引き戸と暖簾が見える。ガラリ。中は凛とした清浄な空間。カウンターの真ん中あたりに座る。大将は物静かな雰囲気であるが、決して無愛想ではない。朴訥かつ穏やかな印象である。
まずはツマミから。雲丹と蓴菜。ありそうでなかなかない取り合わせである。悪くない。あこうはねっとりと口腔にまとわりつき、つぶ貝はコリコリで、うん、と頷く歯ごたえである。炙ったイワシはこたえられない旨さ。続いてタコ、そして漬け込んだ牡蠣。白いのは竹豆腐である。この後、握りますかと聞かれたので、もう少しツマミをと所望する。出されたのはホタルイカの干物とアワビのひもを和えたもの。これは酒の肴であるな。いや、嫌いじゃないけど、もっと肴、もとい魚はないのかしらん。ないのであろう・・・。ツマミをこれでもかと出すタイプの店ではないようなので、握ってもらうことにする。初めてのときは、店の流儀に素直に従う。
最初はキス。瀬戸内育ちの私は、この魚けっこう好きである。イカは細かく刻まれた弥助スタイル(第70夜参照)。たしかお兄さんの店に伺ったときにも、その弥助スタイルについて会話し、尊敬する鮨職人さんですと言っていたような記憶が蘇ってきた。それは、ちゃんと弟さんにも引き継がれている。素晴らしい。こういうの大好きだ。数寄の伝承。鯛もただの鯛ではなく、メイチダイ。極上の白身、高級魚である。アジ、中トロ、トロときて、大好きな鰆の登場である。神戸で鰆はなかなか食べられないのである。それが芦屋にある。そして新子。これだって、昔はお江戸に行かなきゃ食べられなかったものだが、最近はちゃんと関西であたりまえのように出てくるのである。流通と流行に感謝、である。で、鮎の棒寿司が出されるところなど、渋すぎる。続いて、軽く炙った鱧。あいだには、酢味噌が仕込まれている。変化球である。アワビもなかなかの出来栄え。シジミにも驚かされる。普通は椀種で、しかも身は食べない。カッコつけて食べないのである。だがあの滋味たっぷりの出汁を出す貝なのである。旨くないわけがない。そこに目をつけたのだな。う〜んと唸る。もちろん、きちんと仕事がしてあり、たいへんによろしい。車海老、穴子、雲丹。どれも申し分がない。旨い。そして、そして、最後は意表をつく助六が登場する。
ツマミ好きなのでもっとツマミの品数があるほうが好みではあるが、それを差し引いてもネタのバリエーションと構成にアイデアと工夫がある鮨だと思う。トータルで十二分に満足する流れがある。何より、まだ若い店主。これからどんどん進化していくだろうと思わせる余地があり、そこがたいへんに好ましい。
最後の助六の巻きずしがあまりに美味しかったので、つい追加で所望した。お土産に持って帰りたくなるくらい旨い巻きであった。
蛸唐草の地図皿。
このファンキーな伊万里も父のところから我が家にやって来た。本来は皿であるので使うべきであるだろうが、今のところこれに何を盛るのがふさわしいのか考えあぐねているので、もっぱら飾り皿としてのみ存在している。正式には「蛸唐草の地図皿」という。いちおう、憧れの蛸唐草の入った皿ではある。
江戸天保年間には、こんな日本地図が描かれた地図皿がたくさん作られた。真ん中に簡略化された日本地図。まわりの海は蛸唐草でびっしりと埋め尽くされている。地図の部分は型押しによりぽっこりと盛り上がっており、そこに国名が描かれている。この絵柄は19世紀の典型的な流行だったらしく、寺子屋の普及や伊勢参りなどの流行によって大衆文化に勢いがあったこと、さらには伊能忠敬による日本地図の完成などを背景としておおいに流行ったのだという。当時の庶民たちはこういうのを見ながら国の名前とだいたいの位置を知ったのだろうかと思うと、実に興味深い。
絵付けした職人も実際にその地に行っているわけではないだろうから、地図あるいは先に作られた地図皿を見ながら描き写したに違いない。当時は「行基図」という最古の地図があり、どうやらそれに倣ったらしいのだが、「小人国」とか「女護国」などありもしない国名がありもしない位置に描かれている。薩摩の横に突如として現れる大和。これはどう考えても大隅の間違いであろう。京都の場所には平安城、江戸には戊辰城とあるのも、どういう基準で描かれているのだろう。デフォルメされた四国のカタチや微妙にズレている加賀と能登の位置、淡路島と三宅島の大きさがほぼ同じだったり、八丈島にいたっては淡路島より大きい。細かく見ていくと間違いやあれれ?というのがいっぱいあって、眺めていて飽きないし、そのアバウトさが微笑ましく、それゆえに惹きつけられる皿である。
まわりの蛸唐草も典型的な19世紀の描き方で、ぐるぐるっと渦を描いた後、ちょんちょんと蛸の足を簡略化している。私が憧れている伊万里初期の蛸唐草ならば、蛸の足にきちんと輪郭を描き足の中は少し薄い色で塗りつぶす濃淡があり、それはそれは美しいのである。それが、100年、150年経つとこのように簡略化されていくというのも面白い。それだけ大量生産され始めたということでもあるし、ま、空いたスペースとりあえずぐるぐるで埋めとこか、てなイージーさで描いたのではないだろうか。
なんとなく作業場のおおらかな雰囲気と職人たちの能天気さまで想像でき、実に愉快な皿である。
参考サイト
「戸栗美術館」学芸の小部屋
ベーグル&ロックス
ベーグル&ロックス。ロックスはROCKSではなく、LOX。イディッシュ語で鮭の切り身のことをこういうらしい。転じて、スモークサーモンのことを欧米ではロックスと言うのだと教えてもらって、早幾年月。
ベーグルを初めて知ったのはニューヨークでだった。もうかれこれ30年近くになろうか。当時ニューヨークの友人が住んでいたコンドミニアムの近くにおいしいパン屋さんがあり、そこでベーグルを売っていた。ドーナツをふくらませたような形なのに、中身はもちっとしていて密度が濃い。半分にスライスしてもらい中にクリームチーズとスモークサーモンをはさんでもらう。そのスタイルをロックスと呼ぶのである。
ベーグルが面白いのはその製法である。小麦粉を練り発酵させたあと、その生地を茹でるのである。で、オーブンで焼く。この特殊な製法により、外側はカリッとしているのに、中がもっちり、みっしりしたあの歯ごたえが生まれるのである。バターも、卵も、使わない。小麦粉と水だけのストイックなパンなのである。ユダヤ人の多いニューヨークで少しずつ広まって、もはや朝食メニューには欠かせない一品となっている。当時はまだ日本ではほとんどベーグルを売っていなかったので、帰国するとき大量に持ち帰り冷凍しておいたり、一度などは友人が航空便で大量に送ってくれたこともある。ニューヨークや西海岸の食のトレンドが日本で浸透するのに、今でこそほとんど時差がなくなっているが、当時はやはり4、5年はかかった。それが、今ではスーパーでも普通に売られているし、先日などは会社の近くにある超庶民的な天神橋商店街でも専門店を発見した。もうすっかり日本の朝食メニューのバリエーションとして食卓になじんでいるのである。
私は半分に切ったものをカリッとトーストして食べるのが好きで、そこにバターを溶かし、クリームチーズをたっぷり塗った上に、さらにスモークサーモンを乗せる。愛用しているバターはゲランドの塩がジャリジャリ入っているもので、クリームチーズはよつ葉がないときは、キリでもよしとしている。スモークサーモンは成城石井特製。うまい具合に週末にさしかかり、スモークサーモンを土日でちゃんと食べきれそうなときだけ帰りに買って、ベーグル&ロックスでブランチにする。初日は控えめにサーモン二切れであるが、翌日はサーモン三切れ盛りにする。さすがの食べごたえ。ひとり暮らしのささやかな贅沢を噛みしめ、幸せな心地になる。
瑠璃釉の皿。
古伊万里の染付を近頃集めていると骨董好きの父に話したら、瑠璃釉もなかなか捨てがたいぞとこの皿をくれた。もう二十年くらい前のことである。八寸皿と呼ばれる使いやすい大きさで、まさしく瑠璃の色をしている。三枚しかないというのも気に入った。
瑠璃釉は瑠璃呉須とも呼ばれている。呉須を直接刷毛で塗り、その上に石灰釉薬をかけまた呉須を塗る。これを何回か繰り返し焼くことで、瑠璃の色を表現するのである。何度も塗ることから、塗り呉須とも呼ばれているそうだ。
この皿をはじめて見たとき、海の色だと思った。私は瀬戸内海に面した高松市で育ち、(といっても実際は県外の学校から帰省するときにはじめて、瀬戸内海のおだやかさと美しさに気づいたのだが)海といえば真っ先に瀬戸内海の何とも言えないやさしいブルーを連想する。が、これは瀬戸内海というよりは、むしろ日本海の力強く深い青を連想させる色である。いや、実際は、玄界灘を望む地で作られたのだ(ろう)から、日本海から東シナ海を含む大海の色であろう。当然、対馬海流も含まれており、その青は深く底知れない。単純な青ではないような気がする。日本と朝鮮半島の境界にある海。そこには歴史の底に横たわり、葬られて来た小さな物語がたくさんあるだろう。あるいは朝鮮から連れて来られた陶工たちが古里の海の色を偲んで再現しようとしたのかもしれない。そんなふうにこの青は、想像の翼を広げさせてくれるのだ。
ところが、この青を陽の光にあててみると、印象はまたがらりと変わる。底知れなかった深い青は、たゆたう春の海のようなやさしい風情になる。均一だと思っていた表面には、とろりとした水の流れのような景色が現れ、伊万里の柔らかな肌合いとあいまって、何とも言えない優美さが生まれる。こんな効果を意図して釉薬を塗ったわけではないだろうけど、ふとしたときに作為のない美しさが出現するというのが無垢な手仕事の力なのだろう。
この皿も普段の食事に何気なく使っている。たいていは休日の夜であるけれど、光にあてると古里の瀬戸内海のようなやさしさが現れるのなら、早起きして朝ご飯を窓辺でいただくのに使ってみたい。
油面イタリアン「メッシタ」
イタリアは二度しか行ったことがないし、いずれも駆け足だったので、リストランテの食事しか体験がない。それはそれでどの店も感動したけど、もう少しくだけた食堂っぽい店にもチャレンジしたかったなと思う。だけどこの店を知ってからは、わざわざイタリアに行かなくても、予約さえ取れれば、気取らずカジュアルで、美味しいものが食べられるのである。この雰囲気、映画の「かもめ食堂」に似ているような気がしている。あれは和食のお店だったけど、いい素材をあたりまえのようにざくざく使って、自前のレシピと目分量で大胆につくる。店主役の小林聡美が余裕綽々で繰り出すメニューの数々は、シズル感満点で、おなかがぐーっと鳴ったものだ。この店はそのイタリアンバージョンみたいな感じ。私にとっては「鈴木食堂」である。
メッシタという名前は、イタリア語で酒場という意味だそうだ。そうか、食堂ではなくって酒場なのね。近所にあるみんなが気軽に入れる食堂兼酒場。ワインを飲みながら、その日食べたいメニューを選んで、わいわい楽しむ。そんな雰囲気をイメージしてきっと名づけたのだろうなと思う。ネーミングだけとっても、オーナーシェフの鈴木美樹さんの頑としたこだわりが感じられる店である。
初めて行ったときの感動は第89夜を読んでもらうとして、今回参ったのは前にもましての骨太さ。前菜はマグロのカルパッチョなのであるが、なんとクスクスが添えられているのである。「こんな取り合わせ、はじめて食べた」と言うと「シチリアじゃ、リストランテの賄いでポピュラーなので」と返ってきた。ふーん。こういうのを彼の地では賄いで食べるのか。マグロは大胆なぶつ切り。それにまるでチャーハンと見紛うばかりのクスクスが添えられている。が、チャーハンのように重くなく、あくまでも軽い食感。それにしても意表を突く組み合わせである。イタリア人の手にかかるとあのマグロがこうも逞しくなるのかという新鮮な驚きもある。これだけで行ったことのないシチリアを旅している気分になってくる。
続いて驚かされたのは、名物メニューのひとつであるハムカツ。え?これがハムカツ?日本のハムカツの薄くてペラペラしているのをイメージしていると、ものの見事に裏切られます。ハムが立方体。イタリアンな体型のハム。それをカツというよりフリッターみたいに揚げている。ぺらんじゃなくて、ゴロン。凄いボリュームなんである。ところが、衣はもっちりしながら、サクサク軽い。あらら、これならいくつでも食べられそう。ハムの微妙な塩気もいい塩梅。これも彼の地では賄いメニューなのだそうだ。この二品だけでも、私の知っているイタリアンとはずいぶん違う。
鈴木シェフは、都内イタリア料理店に務めた後イタリアでも修行。それを2回繰り返しているが、日本で三度目の修行をした後、再びイタリアへ。三ヶ月で120軒を食べ歩き、帰国してこの店をオープンさせた。知られざる料理法、裏方ならではの工夫、素材との向き合い方を武者修行にも似た食べ歩きで再確認、元々修行していたイタリア料理の腕に、独自の発見が加わったら、怖いものなしである。リストランテのシェフの実力がありながら、庶民的なイタリアの普段のごはんを提供する。これぞ、筋金入りのシェフであろう。その姿勢に惚れる。男だったら嫁さんにしたいと思うだろう(笑)。
さてさて、〆のパスタもこちらの名物ミートソース。これも想像していたのとはまったく違う。ミートソースというよりは肉の細切れが乗っかってるという感じの大胆不敵さ。しっかり塩胡椒されたジューシーなお肉が、太めの麺にしっかりからんで、こたえられないガテン系。トマトのミートソースだけが、ミートソースじゃないことをしっかりと教えてくれるひと皿である。
この日、お隣に座っていた某俳優さんが、美味しい赤ワインを振る舞ってくださった。こういうときは流れにさからわず、素直に有り難くいただく。彼も、鈴木シェフの繰り出す料理のファンであることは、ひととき同じカウンターに座っているだけでよくわかる。
デザートにはクリームブリュレ風のカスタードクリームをいただいた。名前をなんと言うのか失念してしまったが、イタリアのお母さんが作ってくれるスイーツとはこのように甘美なものかと痺れる美味しさだった。
次はいつ行けるだろうな。こんな店があると、東京に住むのも悪くないなと思ってしまう。
大阪南森町「めん坊」
大阪北区紅梅町。昔からずーっとあるうどん屋さんである。独立するまでは勤めていた会社のすぐ近くにあったので、残業するたびに週二三回は通っていたと思う。ここのメインはもちろんうどんであるが、うどん県でもないのになかなかコシのあるいいうどんを打っている。なので、昔からここのうどんだけは普通に食べている。
きつね、卵とじ、昆布、五目、鳥なん、けいらん・・・。ひと通りのうどんはあったのだが、ある夏の日突如として「冷やし焼き豚うどん」というのが出現した。冷やしうどんにトッピングされているのはわかめに温泉卵、気前よくざくざく切った焼き豚にたっぷりの刻みネギ。これにはすっかり参ってしまい、ひと夏中夢中になって食べた。やがてこのメニューは定番化し、ロングセラーとして定着した。
いつの頃からか、残業するときの食事を近所の店に頼むようになったので(第86夜参照)、ここは水曜オンリーの店になった。それと同時に、30年という月日の間に客の利用の仕方も変わり、和の定食や鍋なども充実し、ちょっとした居酒屋感覚の店になってきた。もちろん、我々はいつも残業のための食事をするので、酒は飲まず、サッと入店して、サッと食べ、サッと出る。食べるのは、たいていは丼ものか、焼き魚定食といったもので、もう長年「冷やし焼き豚うどん」があることなど忘れていたのである。メニューもめったに見ることはない。
それがある日、珍しく注文に悩んでメニューを見ていたら、うどんの部に懐かしの「冷やし焼き豚うどん」を発見したのである。さっそく、注文。昔と少し変わったのは、よりヘルシーさを追求してサラダ菜やトマト、玉ねぎのスライスなどが追加されているくらいで、後はなんにも変わらない。焼き豚は噛みしめると、じんわりと肉の旨味を感じる仕上がり。自家製なのだろうか。ていねいに作っていると思われる堂々たる味である。
身体がすこぶる快調で、おなかもそこそこ空腹で、冷たいうどんが食べたいけど、それだけじゃちょっと物足りない。そんな日にぴったりの「冷やし焼き豚うどん」。焼き豚の量があまりに多いので、最近は焼き豚の量だけ半分にしてもらっている。そんなところが、やっぱり歳か(笑)。
「杉本文楽」&「宮本」
友人のガラスアーティスト孝子さんが、杉本文楽に誘ってくれた。なんでも、いい席を取ってくれるお知り合いがいるらしい。で、一枚チケットが余ったので、回會メンバーなら一人くらい誰か行くかしらんと誘いのメールを放った。
ところが、メンバー全員が行くと言い出したのである。
チケットをあと三枚無理してとってもらい、全員参加なら「四回會」ではないかと気づく。幸い、大阪の割烹「宮本」の内装は三浦さんところの三角屋さんの仕事である。一度は三浦さんと行きたいと思っていたのである。当日の次第としては、杉本文楽鑑賞の後、我が社のサロンでしばし休息をとり、夕刻「宮本」へ。その後は都島にある秘密バーを予約した。
回會の掟その一は、「着物を着る」である。一回會のとき、貸衣装だった西井さんは、この日のために着物を誂えるという。ない藤の若旦那が今回もコーディネイトして、西井さんのファースト着物が間に合った。一緒について行った東さんも今後必要になるだろうからと単衣を誂えたそうだ。素晴らしい。そう、単衣があると6月と9月にも回會が開催できる。まことにみなさん、素晴らしい心がけと男気である。
杉本文楽は、大阪フェスティバルホールでの上演。メンバー全員が初文楽だったが、なにしろ松岡師匠が文楽は見ないといけないと常日頃おしゃっているので、全員気合いが違う。本来なら伝統的な文楽を先に見るべきであろうが、杉本文楽は三月現在のトレンドになっているし、今の文楽では上演しなくなっている観音廻りを復活させたという意味でも話題になっている。何であれまず見る、行くということが大事である。
舞台は漆黒の闇である。そこにひとり遣いの人形がすうっと浮かぶ。本文楽では人形遣いの顔は見えるのであるが、杉本文楽では黒装束で顔は見えない。なんでも、人間国宝であろうが顔は隠してもらいますと言ったとか、言わないとか。だから主人公であるお初(人形)だけが闇の中に浮かんでいるのである。バックにはアーティスト束芋によるイラストレーションが動く。観音廻りは注意深く聞くと、韻が重なり、独特の文章であることに気づく。文楽の大夫さんは、歌舞伎とはまた微妙に違っていて、語りが上手い。いわゆる浄瑠璃である。が、節回しも独特だし、この観音廻りを耳だけで理解するのはきわめて難しい。しかし文楽には床本というテキストがあり、わからなくなればこれを見るといいのである。よくできている。(ちなみに本文楽では、ちゃんとこの床本が字幕スーパーで舞台の上に出る。心強い)
杉本文楽、演出はご存知現代美術家杉本博司さんによるものである。本文楽を観たことがない身としては、一体全体舞台が良いのか悪いのかの判断のしようがない。だけど、演目の「曾根崎心中」を歌舞伎では何度も観ているので、筋も展開もわかっている。それをよすがに舞台を観ると、何と言っても物言わぬ人形の表情の豊かさよ。歌舞伎ではお初といえば坂田藤十郎丈で、この人はいくら名優とはいえもう相当なお歳である。近くで観るとビジュアル的にはかなりきついものがある。ところが人形のお初は永遠に年をとらないのである。うつむく姿のいじらしさ。いやいやするときの愛らしさ。遊女とはいえ十九歳の娘の可憐さが感じられるゆえに、ラストで徳兵衛に殺してと乞う素直な一途さが際立つ。そこに絶妙な大夫の語りがかぶされば、もうすっかり文楽にイチコロになる状況はそろっているのだった。
終演後、しばし私のオフィスに移動し、杉本博司さんの写真集や著作を見ながら現代アートについて歓談。時分になったので連れ立って割烹「宮本」へとゆるゆると移動した。入店する前に、全員自前の着物姿を撮影。カウンター8席しかない宮本、回會メンバーにゲスト3名のちょうど8名で貸し切りとなった。都合がよい。多少、騒いでも(騒がないけど)他のお客様には迷惑をかけることがない。
三月の宮本。週が開けると四月なので、もうお膳はすっかり春である。赤貝、鳥貝、みる貝。柔らかな筍に山菜・・・お酒はお気に入りの新政のナンバー6をみんなでぐびぐみ。8人もいるからまたたくまに一升瓶があいてしまった。続いて出されたのが裏鍋島という凝った酒。鍋島という文字を裏にしているラベル。判じ物のようであるが、これは隠し酒ということである。わざわざそれを言わなくても、ラベルでそれがわかる人にはわかるようになっているのが、日本のものづくりの面白さ。これもぐいぐいと飲む。みんなで楽しく、調子よく、飲っていたので、ひとつひとつの料理の記録を取り忘れてしまった。今となっては、何をカウンターで話していたかの記憶もおぼろげではあるのだが、大勢での楽しい時間とはそういうものかもしれない。カウンターだと横一列になるので、途中何度か席替えというのもあった(ような気がする)。宮本さんとも、料理のこと、店のしつらいのこと、うつわのことなどいろいろ話したような気はするのだが、それも覚えていない。が、たいそう充実した時間だったことだけは、確かなことである。
すっかり気分よく出来上がった面々は、今度は秘密のSバー(第53夜・109夜参照)へと繰り出した。この日はお休みであったが、8名で伺うからと無理を言ってお店を開けていただいている。せっかく回會メンバーがそろっているので、あのジントニックを試していただきたいという魂胆である。もちろん、みなさんジントニックの味にも、マスターの語りにも満足していただき、三浦さんなどは予想通りデザートのケーキも美味しいと食べたことは言うまでもない。
杯を重ねた後、京都組はタクシーで帰っていった。大阪泊まりの残り二名におつきあいし、もう一軒バーをはしごして、四回會も無事に終わった。さすがに、今回はシメのラーメンとかの赤提灯系はなかったことに胸を撫で下ろす。
やっぱりフルメンバーだといいね。気合も、意気地も、違う。
◎追記
今回、全員の足元がご存知「祇園 ない藤」御製であるが、右端二人、そして真ん中の私を置いて左の方々がはいているのが、今話題のビーチサンダル『JOJO』である。ビーチサンダルとは思えない出来栄えで、このようなちょっとした遊びのシーンの着物にだって、似合ってしまう。さすがに女性の着物のときはカジュアルすぎるだろうけど、夏の浴衣にはバッチリだし、私はむしろ夏の普段のカジュアルウェアに合わせている。現在、国内だけでなくアメリカ西海岸のセレクトショップでも売られているし、パリでもデビューしている。本体の色、前ツボ、花緒を4色から自由に選べるだけでなく、今年は新色も登場している。
恵比寿「ラ・ベイエ」
5月に続いて今年二回目(第78夜参照)の訪問である。カウンタースタイルの店の楽しみのひとつに、椅子に座ってふうっと一息ついて、「さてと」と、黒板メニューを眺める時間がある。それは、まるで歌舞伎の演目と配役を確認し、うん、この段は気合を入れて観なければと、姿勢を正すのとよく似ている。書かれたメニューからその皿の内容をいろいろ想像したり、どの皿とどの皿を組み合わせようかとあれこれ思案する時間の楽しさよ。シェフにおすすめを聞くのもいい。どんなふうに料理するのか具体的に教えてもらうのもいい。組み合わせるメニューを言ってみて相談するのもいい。いずれにしてもこの作業、その日の食事を盛り上げるためのプレリュード。外せないのである。
前回堪能したアジのマリネを黒板に発見した。前は千葉のアジだったけど、今回は静岡のである。玉ねぎや人参が入っているのは変わりがないが、アジは少し小さめ。シメ具合もキツめ。で、なんとペルノソースで和えられている。ペルノとはアニス系リキュール。水を加えると白濁するヤツで、独特の香りがある。フランスのパスティスとかギリシャのウーゾとか、すべて同じ系統のものである。これをソースにするとなかなかイケる。何より、シメたアジに不思議にマッチするのである。さすが風見シェフ。メニューに変化球を隠し持っている。
スープは冷たいコーン。ていねいに裏ごしして作った一品。本当にトウモロコシって美味しい、としみじみする旨さである。春巻きの中に入っているのは稚鮎である。パリパリの皮の中に初々しい苦味が隠れてい、タルタルソースのほのかな甘味がそれをやさしく包む。うーん。いいね、これ。日本の食材を使い、日本人シェフが作るのだから、美味しくないわけがない。完全なるジャパニーズ・フレンチ。最後は、イカ墨のリゾットアスパラ添え。(ま、パスタとかリゾットがあるなら、フレンチじゃなくってイタリアンじゃないかという疑問は置いといて)このスクエアな皿がまた心憎い。イカ墨の黒と、皿の白、アスパラガスのグリーン、ベーコンの赤。自然の素材だけが表現できる豊穣の色が皿の中にあふれている。イカ墨の微妙な塩気が半生の米の食感にまとわりついて、そのまったり具合をときおりアスパラガスでシャキッと正気に戻す。そんな感じのひと皿だ。
あ〜今日も美味しかった。今日もデザートはお預けである。

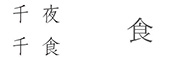



















![th_写真[18]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真182-300x225.jpg)
![th_写真[21]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真212-225x300.jpg)
![th_写真[22]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真222-225x300.jpg)
![th_写真[23]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真232-225x300.jpg)
![th_写真[24]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真241-225x300.jpg)
![th_写真[16]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真163-225x300.jpg)
![th_写真[15]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真153-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真210-225x300.jpg)
![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真114-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真34-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真63-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真45-300x225.jpg)

![th_写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真93-225x300.jpg)
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真103-225x300.jpg)
![th_写真[11]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真115-225x300.jpg)
![th_写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真123-225x300.jpg)

![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真112-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真29-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真33-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真44-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真62-225x300.jpg)
![th_写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真82-225x300.jpg)
![th_写真[7]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真72-300x225.jpg)
![th_写真[11]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真113-300x225.jpg)
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真102-225x300.jpg)
![th_写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真122-225x300.jpg)
![th_写真[13]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真133-225x300.jpg)

![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真110-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真23-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真32-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真43-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真53-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真61-225x300.jpg)
![th_写真[7]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真71-225x300.jpg)
![th_写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真81-225x300.jpg)
![th_写真[11]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真111-225x300.jpg)
![th_写真[16]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真162-225x300.jpg)
![th_写真[17]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真172-225x300.jpg)

![th_写真[18]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真181-225x300.jpg)
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真101-225x300.jpg)
![th_写真[13]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真132-225x300.jpg)
![th_写真[19]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真191-225x300.jpg)
![th_写真[20]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真201-225x300.jpg)
![th_写真[21]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真211-225x300.jpg)
![th_写真[22]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真221-225x300.jpg)
![th_写真[23]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真231-225x300.jpg)
![th_写真[24]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真24-225x300.jpg)
![th_写真[25]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真25-225x300.jpg)
![th_写真[26]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真26-225x300.jpg)
![th_写真[27]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真27-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真42-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真52-300x225.jpg)

![th_写真[13]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真131-300x225.jpg)
![th_写真[16]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真161-300x225.jpg)

![th_写真[17]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真171-300x225.jpg)

![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真17-225x300.jpg)

![th_写真[15]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真151-225x300.jpg)
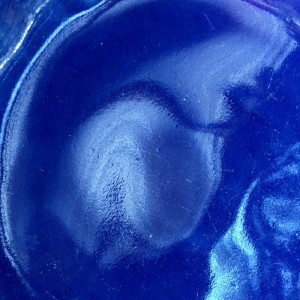

![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真51-225x300.jpg)
![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/写真1-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真21-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真31-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真41-225x300.jpg)
![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真110-225x300.jpg)


![写真[16]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/写真16-300x225.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真2-218x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真3-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真4-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真5-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真6-226x300.jpg)
![th_写真[7]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真7-205x300.jpg)
![th_写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真8-225x300.jpg)
![th_写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真9-225x300.jpg)
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真10-182x300.jpg)
![th_写真[11]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真11-225x300.jpg)
![th_写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真12-225x300.jpg)
![th_写真[13]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真13-225x300.jpg)
![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/th_写真1-225x300.jpg)
![写真[15]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/写真15-225x300.jpg)
![写真[17]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/02/写真17-300x64.jpg)


![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真18-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真25-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真35-225x300.jpg)