2015-01
ベロ藍の印判手。
古伊万里は断然、染付がいい。赤絵とか金襴手は華やかすぎてどうも苦手だ。買い始めた頃いくつかは手を出してはみたものの、結局長いあいだ愛用しているのは藍色の染付なのである。どうしてこんなに染付に惹かれるのだろう、と考えたことがある。「藍」という色は、日本の藍染めをたやすく連想させる。淡いのに深く豊かな色は、なにか日本的心性の奥底にあるものを揺さぶるのである。藍染めに使う藍は植物で、染付の色を表現するのは鉱物という違いはあっても、同じ日本の手仕事の色だからだろうか。
染付の色を出すのには呉須という藍色の染料を使う。多くは中国から茶碗薬という名で輸入されたようだが、原料となる呉須土は瀬戸近辺でも産出されたと聞く。原石を砕き、粉末にし、磁器に文様を描き、釉薬をかけて焼くとあの独特の藍色が現れる。主成分は酸化コバルトで、鉄やマンガンなども含んでいる。中国では染付を青花と言うが、その色は藍ではなくむしろ鮮やかな青、完璧な青という感じがする。日本の染付に淡く枯れたような味わいがあるのは、同じ染料を使っていても釉薬に使われた植物の微妙な違いによるものだろう。景徳鎮はシダの葉を、伊万里はゆすの木の皮を使ったという。まさしく、日本の風土から生まれた枯淡のジャパンブルーなのである。
ところが、主張するクリアなブルーが現れた。明治三年にドイツから安価な酸化コバルト(ベロ藍)が輸入されるようになると、伊万里は一気に大衆化し、大量生産品としてベロ藍の印判手が出回ったのである。ベロ藍とはどうもベルリンの藍がなまったものらしい。呉須より鮮やかなブルーで、パッと目を引く軽妙さがある。印判というのは、江戸期の手描きではなく、銅板、型紙での転写によって柄をプリントするのである。手作業で転写するので、柄にムラが出たり、ズレたりしているのが、かえって味になっている。こんにゃく印判というのもある。まさか本当にこんにゃくに型を彫ったわけではないだろうが、こんにゃくに彫ったとしか思えないようなスタンプ風プリントのことをそう呼ぶ。だが、この大雑把さがよいのである。適当さにホッとする。これはこれで、コレクターもたくさんいるのだ。私も骨董屋めぐりをしているうちに、面白くてつい何枚か買ってしまった。
写真の三枚のうち、左はベロ藍を使った染付、右の二枚はベロ藍の印判手である。なんとか手描きのように見せかけようとしているが、微妙どころか大幅にズレた図柄は印判バレバレである。だけど、そんな細かいことを気にしてないところが、なんともヌケていて、微笑ましく、愛嬌たっぷり。私も何も考えず無造作に使っているが、まったくびくともせず、割れもしない。あろうことか、ときどきは猫の餌皿にもなっている。実に愛い奴である。
神戸三宮「良友酒家」
関西に住んではいるが、そんなに頻繁にお好み焼きは食べない。だが、三宮元町にあるお好み焼き店は好きで、昔はちょくちょく食べに行った。近頃は三宮自体に行くことがめっきり減っているので、年に一度か二度行けれればいいほうである。その年に一二度のチャンスも、定休だか臨時休業だかはわからないけど駄目になってしまった。すっかりお好み焼きの口になっているので、これを他のものに替えるのが非常に難しい。思案しながら歩いていると、中華の看板。お好み焼きから中華への変更はまだなんとかできそうである。それに、この店は前から気になっていた。ひとりでも大丈夫かしらん・・・
ひとりでもまったく大丈夫であった。
ひと皿ひと皿は中華にしては小さめであることをまずは確認する。街場の中華と高級中国料理、前者を0に後者を10にした場合、7.5ぐらいの感覚か。メニューに海鮮如意巻というのを発見した。如意巻というネーミングに感じ入る。うーん、確かに何でも巻こうと思えば巻けるしねえ。見た目もたいそう美しい。芯にはアスパラガス、海老とイカをすり身にしそのあいだに海苔をはさみ、さらに湯葉で巻いて、揚げるという手の込んだ一品である。中華でありながら、半分以上和の領域に踏み込んでいる。塩でいただくというのもなかなかよろしい。はっきり言って旨い。スターターとしては上々である。続いて蒸豆腐餅。これは豆腐のミンチ蒸しであるが、ふわふわの豆腐の中にミンチが隠れてい、葱といい醤油ソースといい、こちらも和のエッセンスが色濃く漂う皿である。何より、豆腐でつくっているというだけで、妙に健康的な雰囲気がするし、軽い食感なのでぱくぱく食べられる。ここまで大正解である。めったに飲まないビールも進む。
〆は海鮮冷麺。やはり夏は冷麺が食べたくなる。こちらのはほうれん草のヘルシー麺に海老、イカ、ホタテ、わかめ、クラゲ、にんじん、きゅうり、もやし、サラダ菜がびっしり乗っており、麺が見えないほどの充実ぶりである。黒ゴマだれをたっぷりかけていただく。うん、なかなかよろし。麺の食感も、たれの味も、私好みである。惜しむらくは海鮮のレベル。この価格でフレッシュを使うのは無理であるのはよくわかっている。もちろん、冷凍ものを解凍しているであろう。それはそれでいいとして、戻し方である。若干ではあるが、ホタテや海老に独特の匂いを感じてしまったのだ。具はひとつひとつ立派で、イカなど丁寧な切り込みが入っている。ちゃんと素材を大事に扱っていることがよくわかるだけに、それだけが残念であった。もちろん、あかん、というレベルではない。あくまでも私レベルのわがままである。
総合力としては、なかなか素晴らしい店であると思う。そこそこの人数で来て、手当たり次第注文してワイワイ言いながら食べまくる、ということを久々にしたくなった。そういうの、昔はよくやったけどね・笑。
南森町の割烹「宮本」
大阪の夏は暑い、暑すぎる。汗だくになって暖簾をくぐる。カウンターの背には床の間がある。掛かっているお軸は、滝。それだけですーっと汗がひくような気がするのだから、まったくもって和の室礼というのは凄いと思う。わずかな空間が演出する季節の涼。そこにある主題を読み解き、季節に重ね合わせ、その日の趣向を推し量る。こんな芸当、日本人にしかできないであろう。
お軸で涼しい気分になったところで、涼感たっぷりの先付けの登場である。ガラスのお皿には、雲丹と夏野菜のゼリー寄せ。雲丹というのはそのままでも、冷たくしても、あっためても、炊いても、焼いても、煮ても、食える奴。素材としての軸がしっかりあるから、どう扱われてもその存在感はそこなわれない。たいした奴である。お椀はいつものお出汁と違って、はまぐりのお汁。こくのある海のエキスがたっぷり。シンプルに三つ葉だけというのがまたよい。お造りは城下鰈、ハリイカ、まぐろ。金彩を施した切子のうつわが素晴らしい。目に涼しく、気持ちにゴージャス。和食というもの、ほんとうに四季折々のうつわで楽しませてくれる。「滝」というお題が、ちゃんと素材とうつわに連なっている。そして夏といえば、鮎。清流を泳いでいたカタチにちゃんと焼かれ、芭蕉をイメージした葉ののうつわに盛られている。蓼酢でいただく季節の味わい。みずみずしい苦味を楽しむ。意表を突かれたのは毛蟹のお鮨。関西で蟹といえば断然冬のずわい蟹だが、夏の毛蟹はやはり旬であるから外せないのであろう。この漆のうつわがまた素晴らしい。漆黒に朱赤。真ん中にこんな小さな一品をぽんと置くだけで、目にも綾なご馳走が完成する。冬瓜のすり流しでちょっと一休み。いよいよ八寸である。視覚の記憶にさきほどのうつわの朱赤がくっきりと残った状態で、今度はほおずきの赤が連打される。鮮やかで、涼やか。表面にはていねいに霧が吹かれている。もうこれだけでご馳走であるのに、ひとつひとつのほおずきの中には、クラゲの酢の物や鱧の子の卵とじ、焼き茄子と海老の和えものがそれぞれ入っているのである。ガラス器のなかには、タコとそうめん南京とオクラの酢の物。自然のカタチも和食では季節を映すうつわになるのだと感嘆。いよいよ〆であるが、ここで関西の夏のもうひとつの代表選手の登場である。そう、鱧だ。クレソンと一緒に鍋仕立てにしていただく。鱧は出汁にくぐらせると歯ごたえに凄みが出る。お出汁と一緒に熱々をいただく。デザートはフルーツのジュレと、ふるふるのわらび餅。最後に小さなお茶碗でお薄が出る。すべていただいた頃には、汗もすっかりひいてゆったりした心地になっている。
「夏はいかにも涼しきように」
利休七則のひとつであるが、昨今のたとえようもない激しい暑さに参っている気持ちが、こちらのカウンターに座り料理をいただいているだけで癒やされた。このまま襖を引くと、よく冷えた隣のお座敷に布団が敷いてあって、そこでうたた寝・・・そんな妄想が頭をよぎった。それがやりたきゃ、旅館に泊まらなきゃ・笑。
神戸鮨「城助」
110夜目にして、とうとうの写真NG店である。別にとくべつに大将が偏固なわけでもなく、高飛車ということでもない。が、写真は撮らせてくれないのである。
ここを教えてくれたのは祇園にある鮨屋の大将である。神戸ならここへ行くと教えてくれたうちの一軒である。同業が休みの日に訪ねる鮨が悪いはずはないし、その祇園の鮨も気に入ったので行く気になった。二回ほど訪れ、キレのある鮨だなと思っていた。ところが、しばらくして電話が通じなくなり、そのうち店を移転したという噂が聞こえて来た。今までは生田門筋から歩いていける場所だったのが、神戸の北野という少し上の方に変わったという。何回電話しても出ないので、しばらく遠ざかっていた。ところがある日、ショートメールが送られてき、そこには「またお待ちしています」というメッセージがあったのである。
それならば。早速、新しい店に出かけることにした。
神戸北野。異人館通りに面したビルの一階。さすがに移転しただけあって、店構えは前に比べると格段に洒落ている。一見さんは少し入りにくいくらいの上品な威圧感。引き戸を引くと、蹲があり、その先にもまた引き戸。間をじゅうぶんに取っており、期待を高めるつくりになっている。中は広々としたカウンター。奥には個室もあるようである。舞台は上々。重畳至極。
ツマミはいきなり、真子鰈の肝巻きからである。肝を身で巻くという変化球。これは、わくわくしてくるではないか。日本酒はおまかせである。奈良御所の篠峯という大吟が出される。限定流通という手に入りにくい酒であるらしいが、これがまた真子鰈によく合う。続いて、たこ。これはもう正真正銘明石のたこである。歯ごたえが違う。そして、あん肝を裏ごしした一品。ここですでに一合が終わってしまう。次に出されたのはキレのある奥丹波。天才杜氏のつくる酒である。貝の出汁が入った茶碗蒸しも旨い。鯖の胡麻和えは、上品な脂に香ばしさがからむ悪魔の誘惑。こういうツマミを出されると、ほんと、酒がぐいぐい進むのだ。で、カラスミの炙り。あきまへんな。ほんま、あきまへん。イワシ、サヨリと続いて、たまらずまた一合。石川の天狗舞五凛。あきまへん。ここまででも、かなりの充実度である。大将は、もともと淡路出身で実家は魚屋であると聞く。淡路の魚屋。こんな太いルートはないだろう。鮨屋にとっては至上のバックグラウンドであろう。
握りは、イカ、アジ、カツオの薫製、キス、かすご、蛤、白えび、のどぐろ、金目鯛と続いた。どれもキリッとした江戸前の握りで申し分ない。そして〆には、鮨飯を揚げたものが出される。これだけは、さすがに撮らせてもらったが、酢飯の味わいがカリカリした食感の中に隠れてい、なかなか旨いのだ。癖になる。
鮨を「寿志」と表記しているのが、大将の気概の現れか。一見とっつきにくい感じもするのだが、話しかければちゃんと気さくにしゃべってくれる。毎日遅くまで店に残り、鮨を研究したり、いろいろなネタを仕込んでいるという。そういう意味では、つねに進化し続けている鮨なのであろう。いずれ、東京進出も考えているという野望も語ってくれた。うーん。やっぱり職人系の人たちは、東京が最終目標になるのだろうかね。こういう店こそ神戸にあってほしいけど、それはこちらの勝手。神戸の鮨にめっきり縁遠くなってしまった今としては、行かないでと言える立場でもない。夜10時以降も入店可能であるらしいので、せめて、半年に一度ぐらいはその進化の方向性を確かめに来なければいけないとな思う。
微塵唐草の古伊万里。
古伊万里の蕎麦猪口を手に入れてから、どうも古伊万里の染付が気になるようになった。雑誌「緑青」や「太陽」などを読み漁り、京の新門前や古門前の骨董屋をのぞいたりし始めた頃、中島誠之助氏の本に出合う。まだ「なんでも鑑定団」で世に知られるずっと前のことだ。中島氏は蛸唐草の名品をたくさんお持ちでグラビアページを眺めているだけでクラクラしたが、すでに江戸期の蛸唐草には高価な値段がついていて到底手が出ない。それに蛸唐草は柄の個性が強烈過ぎて、大事に飾っておくなら別だろうけど日常使うには難しいように思えた。花唐草や萩唐草というのもあったが、私が目をつけたのはみじん唐草である。みじんはあの木っ端微塵の微塵である。江戸も少し時代が下がってくると、花唐草を単純化した文様として出回ったらしい。この記号のような文様はたぶん幕末から明治にかけてのものであろう。これだったら普段に楽しむにはうってつけのように思え、なます皿や猪口などを少しずつ揃えていくことにした。
手前のなます皿と呼ばれるサイズのものは、小ぶりではあるが、それなりの深さがある。なます皿というネーミングからもわかるように、なますを入れるのにちょうどいいのである。江戸の庶民たちが気軽に使っていたカタチというのがよい。私も食卓でおひたしとか、冷奴などを盛るのに愛用している。カステラとかケーキ、和菓子などを盛ってもなかなか具合がよろしい。なにしろ、このカタチ、別名「くらわんか」であるからね。
くらわんか。食らわんか。
そう、このなます皿は別名くらわんか皿とも呼ばれている(茶碗状のものはくらわんか椀)。伊万里やその隣の波佐見でうつわが大量生産され始めると庶民にも出回って、挙句の果てには淀川の飯屋が小舟で川を渡る客に「飯、くらわんか。酒、くらわんか」と呼び込みながら、こういったカタチのうつわに酒や餅などを入れ売っていたのである。客は、食べ終わるとその皿をどぼんと川に捨てるのである。今で言う使い捨ての感覚であろう。まったく、なんという大らかさであろうか、皿を川に捨てるなんて。ひと昔前まで、淀川の川底をさらえばこのくらわんか皿がざくざくと出たこともあるらしい。
ま、このみじん唐草はいちおう唐草であるので、さすがにくらわんか手ではないだろうが、そういった使い方の歴史を知ると、たしかに江戸時代と平成の今も日本は地続きなのである。淀川の底には今もまだ少しはこの手の皿は埋まっているのだろうか。
大阪「Sバー」
ここのことを堂々とは書けない。あくまでこっそりと書いているつもりである。なにしろ紹介制だし、どうも店主のSさんのお眼鏡にかなわなければ、紹介してもらってもそう気軽には出入りできない感じがする。ま、お酒が飲めない人は駄目ですね。あと、騒ぐ人。なので、せいぜい一人か二人、ゆっくりお酒を飲みたいときとか、酒好きな人にスペシャルな心地を味わわせてあげたいとき専用の店である。
今宵は仕事の相棒と。噂のジントニックに感動してもらおうと、取引先のきれいどころも誘っていたのだが、急な体調不良で二人だけとなった。相棒もこの店ははじめてなので、それはそれでよしとする。なんといっても、まずは、例のジントニックに感動してももらわなければ。それにしても、Sさんのつくるジントニックの素晴らしさといったらどうだろう。「森へ散歩に行く感じ」とご本人は表現されるのだが、それだけではない。柑橘の爽快さと高貴な甘さ。そこへ杜松の実の清々しいスパイシーさが合わさって、立体的な針葉樹の森が立ち上がるのである。
前回(第53夜)スペシャルな手作りケーキも美味しいと書いたが、実はサンドイッチも凄いのである。もちろん、事前に今日はサンドイッチもお願いしますと言っておけば、ちゃんとパンも、卵やチーズやバター、野菜も、しかるべきところから仕入れて作ってくれるらしいのである。当然、予約をしなければいけない。ところが、この日もともと4名で予約を入れていたものだから、もし注文があればと、軽い準備だけはしてくれていたのである。そして。「トマトサンドイッチくらいならできます」という幸せな御神託が下ったのである。「二人前ね!」という私を相棒が制し「一人前でじゅうぶんやろ」。え〜、後悔してもしらんけんね。
サンドイッチを一口齧ったときの驚きよ。このできばえの素晴らしさを写真だけで伝えるのには無理があろう。そもそもメインの具がトマトというだけでも、意外であるのに、トマトが立派なメインの具になっているのである。もちろんトマトの吟味というのは必須であろうけど、あんなにある意味みずみずしいものを、パンにはさんで料理として成立させるとは。軽く玉子やハムもはさんではいるが、あくまでメインはトマト。カリカリにトーストされたパンとまたこれが凄い相性なのである。相棒は「もう一人前いけたな」とつぶやく。だから、言ったでしょ。もう遅いわ・・・とぶつぶつ言う私。さほどに、衝撃的なトマトサンドイッチであった。これで、事前にいろいろお願いしていたとしたら、一体どんなサンドイッチを食べさせてくれるのだろう。
この日もレアもののモンテゴメリーズのシングルカスク、アドベッグ・オールモストゼアをちびちび飲りながら、チーズの盛り合わせをいただく。この盛り合わせも凄いのだ。なにしろ、黒板メニューのところに<危険!チーズ盛り合わせ>と書いてあるのだから。もちろん、危険というのは酒が止まらなくなってしまうという意味である。しかも〆に特製ケーキまでいただいてしまった。というか、この店でケーキを食べないわけにはいかないでのある。今夜は、シンプルなパウンドケーキ。てっぺんのレモンシュガーの風味の絶佳なことよ。
この店に連れてってほしい人は、こっそり直メールでリクエストくださいまし。
小鹿田焼の皿。
まだ民藝というものを意識する前に手に入れた皿である。こちらも湯布院で出会った。古伊万里とは対照的な素朴さと力強さがあり、そのどっしりとした存在感に惹かれ、大小の皿と、緑釉のかかった深めの皿をそれぞれ二枚ずつもとめた。
「打ち刷毛目」と「飛び鉋」。小鹿田焼(おんたやき)は刷毛や鉋を使いうつわに独特の文様を刻むのが特徴で、飛び鉋の本歌は宋の修式窯飛白文壺であると言われている。焼かれているのは大分県日田市の山間にある小鹿田地区であることから、この名前がついている。窯が開かれたのは江戸時代。三百年以上の歴史があり平成七年には窯場として初めて国の重要無形文化財に集団指定されているにもかかわらず、陶工たちは作品に銘を入れない。
柳宗悦の「日本民藝美術館設立趣意書」にはこう書かれている。
『 概して「上手」のものは繊弱に流れ、技巧に陥り、病疫に悩む。之に反し名無き工人によって作られた下手のものに醜いものは甚だ少ない。そこには殆ど作為の傷がない。自然であり無心であり自由である 』
反復の作業を続けていくうちに、その繰り返しの仕事が陶工たちの手の熟練を促し、自我が入らない無心の美をもたらしたのだとしたら、このうつわたちはまさにそれを体現している。手に入れてから三十年以上になるが、普段の食事を盛るのにどれだけ使ったか。何を入れてもなじみ、荒っぽい扱いにもにも耐え、一枚として欠けていない。代々その家で使い続けられていくうつわとはこのようなものかもしれないし、これこそが「用の美」というものだろう。
奇しくも、これを書いているときに、日曜美術館新春スペシャル「にっぽん、美の旅」で井浦新が小鹿田の窯元を訪ねる番組を観た。現在ではわずか14軒、そのうちの10軒が昔ながらのやりかたで今も焼ものを作り続けている。この地に伝わる形や模様をたんたんと守っているのだ。小鹿田の土を使い、川にある水車を使い唐臼で土を打ち、その土を女たちが何度も漉し、きめ細かく粘りのある土をつくるのである。陶土にするには、乾燥させ一ヶ月以上かかるという。そうやって女たちがつくる陶土を、今度は男たちが引き取って、形作り、文様を入れ、焼き上げる。気の遠くなるような作業は、紛れもなく家内制手工業である。ひっそりと、たんたんと、無心に、作り続けているのである。ある陶工の言葉が印象的だった。「自然体のみで成り立っているので、自分たちが自然に合わせていくんです。薪も二年以上乾燥させるんで大変ですけど、作業がときに神や仏の領域に近づくことがあって、自然界から教えてもらうことは多い」その陶工の名前は、「工」というのだった。
この飾り気のない「用の美」を、これからも、日々の暮らしのなかで使いこんでいきたい。
海老さまLOVE。
![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/112-e1407065309118-225x300.jpg)
タクシーで歌舞伎座へ向かっていたときのことである。運転手さんが「歌舞伎を観に行くお客さんをよく乗せますけど、海老蔵はやっぱり昔の役者に比べるとまだまだらしいですねえ」と言う。「え、どなたがそんなこと」と問えば、年配の見巧者からよくそういう風に言われるのだそうだ。そして必ず同時に語られるのが例の西麻布の事件のこと。真相もいきさつもよくは知らないし、第一そんなことはどうだっていい。役者は舞台の上で感動させてくれれば私生活など関係ない。そもそも、歌舞伎役者は傾いてこそ値打ちがある。
運転手さんにはこう話した。「新之助時代の終わり頃から熱心に見ているけど、格段に成長しています。もう観られない昔の役者と比べることはできないけれど、新之助から海老蔵、そして團十郎へと大きな役者になっていくのを見守るのがファンというもの。なによりその成長の過程を同時代人としてリアルに感じられる喜びは格別ですよ」すると運転手さんは感に堪えない様子で「お客さん、凄いなあ。この話、タクシーの詰め所でみんなに言っていいですか」と言う。ふふ。どうぞ、どうぞ。私の心意気にまいったか。ファンとはそういうものである。
海老蔵なんて、とマスメディアのイメージだけで語る人は多い。だけど一度でも海老さまの舞台を観たらそんなことは言えなくなる筈だ。まだまだオールマイティとは言えないし、精進の過程にあるにはあるが、海老さまにしかできない演目はずいぶんと増えてきたように思う。
市川宗家の十八番と言われる荒事、鳴神や毛抜、助六や勧進帳なのスーパーヒーロー役などはもうすっかり海老さま独自の世界が構築されていて安心して見ていられるし、先代の猿之助に教えを乞うて作り上げている伊達の十役、義経千本桜の四切などはもうほかの役者の追随を許さないレベルにきているのではないか。新作の石川五右衛門や「色悪」と呼ばれるたとえば源氏店の与三郎や女殺油地獄の与兵衛なども彼独特の容姿もあいまってぞくぞくするほどの色気がある。最近では七月歌舞伎の「夏祭浪花鑑」の団七に鬼気迫るものがあった。間近で観ていて真剣に人間の心に潜む闇というものの怖さについて考えさせられてしまった。
近頃はABKAIと銘打って積極的に自主公演を企画したり、歌舞伎×オペラ×能とのコラボレーション舞台にもチャレンジしている。こうも矢継ぎ早にいろんな舞台を企てているその裏には、このままにしていたら歌舞伎を楽しむ人がどんどん減っていく。若い世代を取り込んでいかなければ歌舞伎の未来はない。なんとかしなければ。そうした切迫したおもいが潜んでいるように思う。團十郎さんが逝って一年と半年。市川宗家の伝統歌舞伎をしっかり守りながらも、利用できるメディアはしっかり利用させてもらっていずれ若い人たちを舞台に呼びたい。海老様はきっとそう思っているはずだ。
たぶん、今はもう少し海老蔵としてやりたいことすべてにチャレンジしながら己れを磨き、精進し、研鑽を積み、満を持して来るべき十三代目の襲名を迎えるのだろう。その日まで、活きのいい海老が跳ねるのを思う存分に楽しみ、味わい尽くしたい。
◎海老様の本はいろいろ出ているが、村松友視氏のこれはなかなかよい。
アマゾンで村松友視著『そして、海老蔵』を購入
◎茂木さんとの対談集も。
アマゾンで『市川海老蔵 眼に見えない大切なもの』を購入
アジアン食堂「チャムチャ」
田原陶兵衛さんの萩焼と出逢って(第106夜参照)、30年前の記憶が鮮やかに蘇ってきた。旅の相棒としてさまざまな場所に一緒に取材に出かけた彼女のことである。当時一緒に仕事していたカメラマン・通称おじいちゃんのアシスタントだったなおちゃんである。アシスタントといってもおじいちゃんが信頼している右腕のような存在で、おじいちゃんの人柄もあって彼がリタイアするまでつねに傍らにいた人である。
当時、我がクライアント様もかなりの太っ腹で、情報誌のためにどこでもいいから海外取材してくれと今では考えられないようなオファーをくれていた。ジャマイカ、スペイン、マルティニーク・・・。そのうち、インドネシア、シンガポール&マレーシアなど近隣諸国にはなおちゃんとふたりで行くようになった。萩行きもその一連で訪れた。行きたい場所を決め、全体構成をつくり、取材して写真を撮る。私が後に自分でも一眼レフカメラを持ち、ひとりで取材に出かけるようになったのはなおちゃんとの旅の経験なくしてはありえなかった。その頃、なおちゃんがプライベートでもよく行っていたのがバリ島である。バリ島取材のとき、インドネシア語も含め、アジアへの知識に舌を巻いたことをよく憶えている。そのうち、インドネシアからインドやネパールにも興味を広げて行ったと聞く。
おじいちゃんがリタイアすることとなり、なおちゃんはそれを機にカレー屋をやりたいと開店の準備を始めた。それからしばらくして店をオープンしたとの案内ももらっていたのだが、本当に不義理をしてしまい長い間訪れることができなかった。それが、萩焼と30年ぶりの邂逅を果たし、急になおちゃんと行ったあの旅のことを鮮明に思い出し、店というよりなおちゃんに無性に会いたくなったのである。
店があるのは西天満。えべっさんで有名な堀川戎神社のすぐ南にある。2年ぶりぐらいに会うなおちゃんは、昔と変わらないノーメイクとヘアスタイル。真剣に調理台に向かう表情はカメラに向かっていた昔と変わらない。変わったのは光を調整する露出計を持つ代わりに、包丁やフライパンを握っているということくらいか。ランチにいただいたネパールカレーは想像以上にスパイシーで美味しかった。一緒についてくる豆のスープをカレーにかけると、また味わいに深い奥行きが出る。ネパールカレーの辛さはひと方向への単調なものだと思い込んでいた私の先入観は、なおちゃんのカレーで見事にくつがえされた。
ランチは、3種類のカレーの中から選べ、野菜のスパイスサブジ、サラダ、自家製ピクルス、ターメリックライスでなんと700円である。夜は、カレーだけでなく、なおちゃんがアジア各地を食べ歩いてこれは、というものを彼女独自のアレンジで食べさせる。インド豆のせんべい、ネパールのポテトサラダ、タイの春雨サラダ、ネパールの小籠包、ネパール風豆のパンケーキ、海老の春巻き、チャウメン…。お酒はネパールのラム酒にインドワイン、マッコリまである。
夜は夜で、ちゃんと来てみたい店である。なにより、露出という光の調整をいつも真剣にやっていた人が、今はキッチンでスパイスや調味料をじつに見事に加減しているのだ。その料理がおいしくないわけないもんね。
長門駅前鮨「はしもと」
どこに行っても鮨屋があれば、つい行きたくなる。鮨屋には地元で穫れる魚がある。地酒もある。その土地ならではの作法や独特の食べ方もある。鮨を通じてだって、日本の文化人類学は楽しめるのである。地方でも都市ではなく、こういった鄙びた駅前(失礼)の鮨屋とはいったいどういう具合になっているのか知りたくてたまらない。
文楽終了後、長門駅発の電車に余裕があったので、タクシーの運転手さんに駅の近辺に鮨屋があるかどうか聞いてみた。すると「はしもと」を推奨され、横付けしてくれたのである。時間はまだ早いので予約なしでも大丈夫であろう。むろん、店内はガラガラで私一人だけだった。家族経営らしく、おかあさんのような人が相好を崩し、どうぞ、どうぞと招き入れてくれた。カウンターの中程に陣取る。
さてと。店内を見渡すと獺祭があるではないか。さすがに磨き二割三分はないがちゃんと純米大吟醸の50というのがある。たしかに、地元の酒が地元で飲めないのなら地酒の意味はない。「音信」でも、磨き二割三分は宿泊者二本限定で販売していた。さっそくグラスで所望する。
おかあさんが、「私のつくった鯵の南蛮漬け、食べてな〜」とスペシャルな一品を出してくれる。こういう出合はたまらない。はしもとさんちの鯵、もとい味。たまねぎなんぞざくざくと切られてい、酢加減もきわめて素朴なおふくろの味。こういうお惣菜を鮨の前にいただくと舌が違う方向に行ってしまうよと思いながらも、ご好意に甘える。これをアテに獺祭を飲むというのはご当地ならではのファンキーなスタイルではなかろうか。
鮨の前にやはりツマミ系は行きたいので、おすすめの刺身を盛り合わせにしてもらう。はまち、ヒラメ、鯛、カワハギ、ホタテ、金目鯛・・・。とくべつにこの辺だけで穫れる魚はないけれど、この椀飯振舞っぽいひと皿を独り占めできるのはお大尽気分である。そして上握り10カン。シャリは少し少なめにしてもらったが、けっこうなボリュームである。きわめて真っ当な握りの盛り合わせ。それでも軍艦の中にヒラメの縁側が入っていたりすると、おおうなんだかこのスタイルご当地ねえという気分になってくる。
こういったはじめての店にひとりで入り、酒を飲んでいると、たいていはこの女何者かと誰何されることが多い。もちろん近頃のことであるので、そうあからさまに聞いてくる訳ではないのだが、それでもどうしてこんなところで飲んでいるのか、何のためにこの地に来たのか、鮨はどこどこに行っているのかなど、けっこう質問攻めに合うのである。こういうのは、居合いのようなものだと思っている。饒舌にならず、言葉少なに、こちらの正体をうまい具合に想像させる。今回は文楽を鑑賞しに神戸から来たというと急に態度がフレンドリーになった。というのも、こちらの大将は神戸でも修行をしていたとのこと。話をしていると共通の知っている店があったりしてそれはそれで愉快であるし、長門の文楽というのは今や夏の風物詩であるらしい。それだけで距離がぐんと近くなったりする。
カウンター後ろの座敷に入って来たカップルが、あ、こっちも獺祭をとリクエストしながら、しきりに近頃獺祭が気軽に飲めなくなっていることを嘆いている。今や、地元でも手に入りにくくなっているらしい。こういう現象、獺祭だけじゃない。大間のマグロだって地元の人はほとんど食べられないらしいし、松葉ガニや越前ガニ、関サバとか、旨い、美味しいと言われるものはクオリティの高いものから中央に行ってしまう。値段にはプレミアムがついてしまう。いいものは高くても売れるというのは資本主義社会としてあたりまえのことだし、それに価値を見いだす人がいる以上その現象を否定するつもりもないけれど、地の利ということがないとその土地は報われない。その土地に足を運んでこそ、得られる、経験できるもの。そういうコトやモノがもっともっとたくさん地方にキープできればよいなと思う。それでこそ地産地消ブームが本物になる。
というわけで、また獺祭を飲みに(もちろん文楽も観に)来年の夏来たい。
◎追記
獺祭は、かわうその祭りと書く。かわうそは、摑まえた魚を川岸にずらりと並べる習性があり、獺祭というのはこのことを指す。私がこの興味深い話を知ったのは向田邦子さんの名著「かわうそ」というエッセイによってである。この短編は何度読んでも、圧倒され、恐ろしく、心に刺のようにささって、まさしく向田邦子さんを代表する名作だと思う。
古伊万里の蕎麦猪口。
もう三十年以上前のことだ。湯布院に取材にでかけ、帰る前に立ち寄った小さな骨董屋でみつけた古伊万里。時代はそれほど古くはない。高台は直径に比べるとかなり小さい、いわゆる蛇の目高台。せいぜい幕末ぐらいであろうか。だけど、それは小さいのにとてつもなく光って見えた。たしかひとつ一万二三千円だったように思う。当時の私にはとても高価に感じられた。だけど、ほしいという気持ちと、これを手に入れることで少し違う世界に足を踏み入れることができるのではないか。そんな期待感があった。悩んだあげく、矢羽根と格子を二つずつもとめた。はじめて自分で買った小さな骨董である。立原正秋の小説を読みふけっていたおかげで、すでに伊万里や唐津、李朝などのうつわについての多少の知識もあり、いつかは身銭を切って買ってみたいという気持ちもあった。今から思えばたいした金額でも行為でもないが、まだ二十代だった私にはなにかひとつ境界を超えたという妙な意識の高ぶりがあった。
今見てもこの蕎麦猪口は愛おしいし、何度眺めても、触っても、心が震える。色あせた呉須の線はきっぱりと潔く、意図せずゆがんだ線には、職人の作為のないのびやかな精神が息づいているような気がする。ためつすがめつ眺め、手のひらで弄び、お茶もそばつゆもほとんど入れることなく、ただただ愛でているうちに三十年が経ってしまった。だけど、この蕎麦猪口を見るだけで、あの日の湯布院で店主と交わした会話すら蘇ってくるのである。人生の中に、あざやかな句読点を打ってくれた買い物である。ひとつはうっかり落とし口の部分を割ってしまった。すでに金継ぎセットも買っているのだが、いまだに手をつけられないでいる。
もう少し先。仕事も一段落して、趣味の世界に心ゆくまで没頭できるようになる余裕ができたら、毎日料理を楽しんで、うどんやお蕎麦のつゆを入れるのはもちろん、ぬたを盛ったり、白和えなどを入れ、普段の食卓に活躍させたいと思う。こういう手のこんだちょこっとした一品を入れるのに「おちょこ」はちょうどいい。

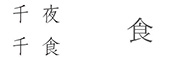






![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真16-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真24-225x300.jpg)

![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真14-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真23-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真33-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真42-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真52-225x300.jpg)
![th_写真[6]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真62-225x300.jpg)
![th_写真[8]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真81-225x300.jpg)
![th_写真[9]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真9-225x300.jpg)
![th_写真[10]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真10-225x300.jpg)
![th_写真[12]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真121-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真22-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真32-225x300.jpg)



![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真12-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真21-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真31-225x300.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真41-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真51-225x300.jpg)
![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/13-e1406996220656-225x300.jpg)
![写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/32-e1406996306220-225x300.jpg)
![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/th_写真1-300x216.jpg)

![th_写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真11-225x300.jpg)
![th_写真[5]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真5-225x300.jpg)
![th_写真[トップ]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真トップ-225x300.jpg)
![th_写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真2-225x300.jpg)
![th_写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真3-300x225.jpg)
![th_写真[4]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2015/01/th_写真4-300x225.jpg)
